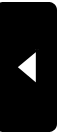【残念なお知らせ】諸般の事情により、クォーター大阪暮らしは2009年11月末をもって終了することとなりました。これまでのご愛顧に心より感謝申し上げます。今後はこちらのブログで記事を提供してまいります。よろしくお願いします。
2009年04月09日
「付録」が大人気のアラサー女性誌
先日の当ブログでは、タクシー会社の「生活支援サービス業」への取り組みについての記事を取り上げました。この記事に関連し、セルフイメージを変えることの意義について述べました。
嬉しいことに、ブログの内容に「感動した」とのメールをいただきました。明確なセルフイメージを描くことや、それを変革することの重要性を、ご理解いただいていらっしゃるのでしょう。ありがとうございます。
とは言え、実のところ、セルフイメージが「独りよがり」では困るということもあります。企業の場合は特に、顧客や市場からどのようなイメージで見られているか、常に意識しておく必要があるからです。
顧客や市場が自社に抱くイメージについては、それが肯定的なものであればあるほど、変えることにはリスクを伴います。「そんな風に見られたくない!」というプライドは、まさに「独りよがり」なのです。
4月9日付けの日経産業新聞に、「30歳前後のアラサー女性誌分野でトップの発行部数を誇る」という「Sweet(スウィート)」という雑誌についての記事が掲載されています。
記事によれば、「11日に発売する5月号は過去最高の60万5千部を発行し、4月号の46万部から急伸する」というから、スゴいです。この人気の秘密は「付録にある」のだそうです。
5月号の付録は「Cher」のトートとポーチのセット。私にはよくわからない世界なのですが、基本的には「バッグ類が人気」だそうです。「どのブランドと組むかで買い手の反応が変わる」とか。
要するに、雑誌としての「企画の内容よりも付録の存在」の魅力が、発行部数に直結しているわけです。それが読者に支持されているのです。既にそのイメージも確立されているのでしょう。
ですが、発行部数が伸びるのはよいものの、「雑誌を作る者として読者を付録で釣るうしろめたさがあった」そうです。そこで付録を外した号を発行したこともあるのですが、「見事に売れなかった」とは・・。
雑誌として「こうありたい」と描いたセルフイメージは、市場に受け入れられなかったというわけですね。今ではもう「吹っ切れた」そうで、「本の作り手にありがちなプライドは捨てている」とのことです。
価値観の問題でもあるので、市場に抱かれているイメージに迎合することが常に正解だとは言いません。ですが、セルフイメージとのギャップがあれば、それなりの結果しか出ないということは、覚悟しなければなりません。それが厳しい現実です。
市場が自社に抱いているポジティブなイメージは、市場に認められた「強み」だと認識すべきでしょう。「選択と集中」の原則からすれば、「強み」をさらに磨きあげていくことが、戦略的には正解となります。
この記事のケースのように、付録の魅力が発行部数を押し上げていることを知りつつ、「確信犯」的に付録を外したのであれば、すぐに修正がききます。
ですが、恐ろしいのは、市場とのイメージのギャップに気づかないケースです。「強み」を勘違いし、全く間違った方向へと経営資源を集中投下してしまうことになるからです。
顧客の声に耳を傾けることは、そのような「勘違い」をしないためにも重要ですね。「なぜ、他社からではなく、わざわざわが社から買ってくれるのか」。簡単な質問ですが、まずはこれを顧客に投げかけてみることをしてはいかがでしょうか。
【今日の教訓】
あなたが自社に対して抱くセルフイメージは、市場・顧客が描くイメージと一致しているだろうか。間違った方向へ努力することをしないように、顧客の声に耳を傾けてみよう。とんでもない「勘違い」をしているかも知れない。
<参考:日経産業新聞 2009.04.09【6面】>
嬉しいことに、ブログの内容に「感動した」とのメールをいただきました。明確なセルフイメージを描くことや、それを変革することの重要性を、ご理解いただいていらっしゃるのでしょう。ありがとうございます。
とは言え、実のところ、セルフイメージが「独りよがり」では困るということもあります。企業の場合は特に、顧客や市場からどのようなイメージで見られているか、常に意識しておく必要があるからです。
顧客や市場が自社に抱くイメージについては、それが肯定的なものであればあるほど、変えることにはリスクを伴います。「そんな風に見られたくない!」というプライドは、まさに「独りよがり」なのです。
4月9日付けの日経産業新聞に、「30歳前後のアラサー女性誌分野でトップの発行部数を誇る」という「Sweet(スウィート)」という雑誌についての記事が掲載されています。
記事によれば、「11日に発売する5月号は過去最高の60万5千部を発行し、4月号の46万部から急伸する」というから、スゴいです。この人気の秘密は「付録にある」のだそうです。
5月号の付録は「Cher」のトートとポーチのセット。私にはよくわからない世界なのですが、基本的には「バッグ類が人気」だそうです。「どのブランドと組むかで買い手の反応が変わる」とか。
要するに、雑誌としての「企画の内容よりも付録の存在」の魅力が、発行部数に直結しているわけです。それが読者に支持されているのです。既にそのイメージも確立されているのでしょう。
ですが、発行部数が伸びるのはよいものの、「雑誌を作る者として読者を付録で釣るうしろめたさがあった」そうです。そこで付録を外した号を発行したこともあるのですが、「見事に売れなかった」とは・・。
雑誌として「こうありたい」と描いたセルフイメージは、市場に受け入れられなかったというわけですね。今ではもう「吹っ切れた」そうで、「本の作り手にありがちなプライドは捨てている」とのことです。
価値観の問題でもあるので、市場に抱かれているイメージに迎合することが常に正解だとは言いません。ですが、セルフイメージとのギャップがあれば、それなりの結果しか出ないということは、覚悟しなければなりません。それが厳しい現実です。
市場が自社に抱いているポジティブなイメージは、市場に認められた「強み」だと認識すべきでしょう。「選択と集中」の原則からすれば、「強み」をさらに磨きあげていくことが、戦略的には正解となります。
この記事のケースのように、付録の魅力が発行部数を押し上げていることを知りつつ、「確信犯」的に付録を外したのであれば、すぐに修正がききます。
ですが、恐ろしいのは、市場とのイメージのギャップに気づかないケースです。「強み」を勘違いし、全く間違った方向へと経営資源を集中投下してしまうことになるからです。
顧客の声に耳を傾けることは、そのような「勘違い」をしないためにも重要ですね。「なぜ、他社からではなく、わざわざわが社から買ってくれるのか」。簡単な質問ですが、まずはこれを顧客に投げかけてみることをしてはいかがでしょうか。
【今日の教訓】
あなたが自社に対して抱くセルフイメージは、市場・顧客が描くイメージと一致しているだろうか。間違った方向へ努力することをしないように、顧客の声に耳を傾けてみよう。とんでもない「勘違い」をしているかも知れない。
<参考:日経産業新聞 2009.04.09【6面】>
2009年04月08日
なぜアフターフォローが大事なのか。
人口が減少へと向かっている時代は、既存顧客をリピーター(得意客)化することが大切です。アフターフォローを熱心に行なうことで、反復購買へとつなげ、長期間でみた顧客単価を最大化できるからです。
自動車であれば、買い替え時期を逃さないためにも、顧客との関係は維持しておきたいものです。住宅も、リフォームなどの需要取り込みのために、しっかりと囲っておきたいことでしょう。
4月8日付けの日経MJ(流通新聞)に、「明治安田生命保険が元気だ」という記事が掲載されています。「2008年度の新規契約年換算保険料は2年ぶりに前年度を上回ったもよう」だそうです。
その要因として記事は、「新規契約の獲得より、既存顧客のアフターフォローを重視したことが結果的に契約者増につながった」ことだとしている。既存顧客のアフターフォローは、契約を維持するためと考えられがちだが、実際には新規契約が生まれているという点が興味深いです。
要は、「顧客の満足度が高ければ家族や知人、友人などへの紹介が自然と増え」るということのようです。記事によれば、保険の営業職員の場合、「契約数に応じて給料が決まる歩合給では新規契約の獲得に意識が向きがち」となってしまいます。
ですが、「急がば回れ」です。「優秀な営業職員はすでに契約をしている既存顧客を大切にする」とのこと。それが結果として、新規顧客の紹介に結びつくわけです。
明治安田生命保険の場合、「営業職員約3万人のうち優秀な上位20~25%の行動様式を調べ」、その結果から得られた「共通項」が、アフターフォローだったのです。
アフターフォローが大切だということは、観念的には誰もが理解していることでしょう。とは言え、それが新規契約につながるということまでは、認識していのではないでしょうか。記事自体、「意外な共通項」と表現しています。
必ずしも明確な差別化ポイントがみられない、保険という商品の特性も影響しているのでしょうが、いずれにしろ、優秀な営業職員の行動様式という客観的データから導き出された結論だから、説得力があります。
アフターフォローの重要性を理解させるだけでなく、実際に行動を起こさせることが、さらに大切だと言えます。そこで明治安田生命では、「安心サービス活動制度」を実施しています。
これは、「営業職員に期待する標準的なアフターサービスを明確にし、実践状況をポイント化して評価する」というもので、しっかりとフォローすればするほどポイントが付与される仕組みになっています。
月に獲得すべきポイント数が決まっているので、客観的に測定でき、強制力もあります。「仕組み」とは、このようなことですね。アフター
フォローをしっかりしろと、口で言うだけでは不十分なのです。
さらに、「社内教育検定制度」を実施し、自信を持ってアフターフォローに出向くための条件を整備しています。アフターフォローという戦略、「安心サービス活動制度」、「社内教育検定制度」のいずれも、数値の裏付けや基準に拠るもので、理詰めの施策です。
この仕組みが完全無欠なものとは言いいませんが、方針を具現化していくために、お題目を唱えるだけでなく、打つべき手はしっかり打っているという点は、見習いたいところです。
【今日の教訓】
あなたの企業では、自社の戦略を決定し、それを実現するために、どのような手を打っているだろうか。数字による裏付けや行動基準を明確に設定しているだろうか。本気で戦略を実現したいのなら、徹底的に理詰めで考え、手を打っていこう。
<参考:日経MJ(流通新聞) 2009.04.08【3面】>
自動車であれば、買い替え時期を逃さないためにも、顧客との関係は維持しておきたいものです。住宅も、リフォームなどの需要取り込みのために、しっかりと囲っておきたいことでしょう。
4月8日付けの日経MJ(流通新聞)に、「明治安田生命保険が元気だ」という記事が掲載されています。「2008年度の新規契約年換算保険料は2年ぶりに前年度を上回ったもよう」だそうです。
その要因として記事は、「新規契約の獲得より、既存顧客のアフターフォローを重視したことが結果的に契約者増につながった」ことだとしている。既存顧客のアフターフォローは、契約を維持するためと考えられがちだが、実際には新規契約が生まれているという点が興味深いです。
要は、「顧客の満足度が高ければ家族や知人、友人などへの紹介が自然と増え」るということのようです。記事によれば、保険の営業職員の場合、「契約数に応じて給料が決まる歩合給では新規契約の獲得に意識が向きがち」となってしまいます。
ですが、「急がば回れ」です。「優秀な営業職員はすでに契約をしている既存顧客を大切にする」とのこと。それが結果として、新規顧客の紹介に結びつくわけです。
明治安田生命保険の場合、「営業職員約3万人のうち優秀な上位20~25%の行動様式を調べ」、その結果から得られた「共通項」が、アフターフォローだったのです。
アフターフォローが大切だということは、観念的には誰もが理解していることでしょう。とは言え、それが新規契約につながるということまでは、認識していのではないでしょうか。記事自体、「意外な共通項」と表現しています。
必ずしも明確な差別化ポイントがみられない、保険という商品の特性も影響しているのでしょうが、いずれにしろ、優秀な営業職員の行動様式という客観的データから導き出された結論だから、説得力があります。
アフターフォローの重要性を理解させるだけでなく、実際に行動を起こさせることが、さらに大切だと言えます。そこで明治安田生命では、「安心サービス活動制度」を実施しています。
これは、「営業職員に期待する標準的なアフターサービスを明確にし、実践状況をポイント化して評価する」というもので、しっかりとフォローすればするほどポイントが付与される仕組みになっています。
月に獲得すべきポイント数が決まっているので、客観的に測定でき、強制力もあります。「仕組み」とは、このようなことですね。アフター
フォローをしっかりしろと、口で言うだけでは不十分なのです。
さらに、「社内教育検定制度」を実施し、自信を持ってアフターフォローに出向くための条件を整備しています。アフターフォローという戦略、「安心サービス活動制度」、「社内教育検定制度」のいずれも、数値の裏付けや基準に拠るもので、理詰めの施策です。
この仕組みが完全無欠なものとは言いいませんが、方針を具現化していくために、お題目を唱えるだけでなく、打つべき手はしっかり打っているという点は、見習いたいところです。
【今日の教訓】
あなたの企業では、自社の戦略を決定し、それを実現するために、どのような手を打っているだろうか。数字による裏付けや行動基準を明確に設定しているだろうか。本気で戦略を実現したいのなら、徹底的に理詰めで考え、手を打っていこう。
<参考:日経MJ(流通新聞) 2009.04.08【3面】>
2009年04月06日
視点が変われば、行動も変わる。
コーチングの事業への取り組みを始めてから、8年以上になります。なぜコーチが必要なのか。さまざまな理由がありますが、「自分一人では出来ないことがあるから」ということも、一つの模範解答でしょう。
ごくわかりやすい例で言えば、自分の背中についたゴミは、自分では気づかないものです。気づかなくて当たり前ですよね。ですので、コーチを雇う必要があるのは、クライアントに欠陥があるからだと考えなくてよいのです。
立場が変われば、視点も変わるので、見えるものが違ってきます。コーチを雇うことで、別の視点を得ることができます。それが実に貴重なのです。
企業がコンサルタントを雇うのも、外部の専門家たる第三者の視点で自社をみて欲しいという動機があったりします。社内のさまざまなしがらみから自由であることが、コンサルタントの強みだと言えるでしょう。
もちろん、コンサルタントの目に何が映ろうと、最終的に意思決定を下すのは、トップの仕事です。また、企業を改革していくには、トップダウンで進めなければならないことが多いものです。
4月6日付けの日経MJ(流通新聞)に、「イオンは衣料品や食品など、取扱商品の品目数を4割削減する計画だ」という記事が掲載されています。
記事は、品目数を削減を妨げるさまざまな要因を述べ、そして最後に、「難題の克服はトップの裁量に左右される。岡田元也社長の陣頭指揮による迅速な改革が求められている」と結んでいます。
品目数を削減するメリットについて、記事は、「一品当たりの販売数量が増え、仕入価格が下がる。作業効率が改善され、生産性が向上する」と解説しています。
さらに、「イオン以外の総合スーパーや百貨店でも過去、何度も叫ばれてきた。だが、思うようには進んでいない」とも指摘しています。要因として、バイヤーの縄張り意識などが挙げられています。
バイヤーには、会社の方針とは別の論理が働いているわけですね。「立場が変われば視点も変わる」とは、このようなことでしょう。だからこそ、それを超越した「トップの裁量」が必要となるわけです。
これは、検事や弁護士が裁判官を兼務しないのと同じことです。兼任させておきながら判決結果を批判しても、どうにもなりません。仕組みを変えなくてはならないのですから。
記事はその点について、バイヤー数を減らすことと、「売上高だけでなく粗利(または営業利益)でも管理することが肝心だ」と指摘しています。これは、バイヤーの視点を変える方策だと言えるでしょう。
視点が変われば、行動が変わります。今まで見えていなかったものが見えるようになり、それが「気づき」を生むからです。「気づき」を得ずして、人はなかなか、行動を改めるものではありません。
「トップの裁量」は、どこに視点を向けよ、と示すことに発揮されます。品目数の削減は「結果」に過ぎず、それを達成するために必要なのは、その結果に至るプロセスを変えることであり、それには視点の移動が必要だからなのです。
【今日の教訓】
あなたは経営者として、自社の従業員の視点をどこに導いているだろうか。今までとは異なる方針を徹底したいと思うのなら、視点を変えることを促す必要がある。それを実現するために、経営者としてのリーダーシップを発揮しよう。
<参考:日経MJ(流通新聞) 2009.04.06【3面】>
ごくわかりやすい例で言えば、自分の背中についたゴミは、自分では気づかないものです。気づかなくて当たり前ですよね。ですので、コーチを雇う必要があるのは、クライアントに欠陥があるからだと考えなくてよいのです。
立場が変われば、視点も変わるので、見えるものが違ってきます。コーチを雇うことで、別の視点を得ることができます。それが実に貴重なのです。
企業がコンサルタントを雇うのも、外部の専門家たる第三者の視点で自社をみて欲しいという動機があったりします。社内のさまざまなしがらみから自由であることが、コンサルタントの強みだと言えるでしょう。
もちろん、コンサルタントの目に何が映ろうと、最終的に意思決定を下すのは、トップの仕事です。また、企業を改革していくには、トップダウンで進めなければならないことが多いものです。
4月6日付けの日経MJ(流通新聞)に、「イオンは衣料品や食品など、取扱商品の品目数を4割削減する計画だ」という記事が掲載されています。
記事は、品目数を削減を妨げるさまざまな要因を述べ、そして最後に、「難題の克服はトップの裁量に左右される。岡田元也社長の陣頭指揮による迅速な改革が求められている」と結んでいます。
品目数を削減するメリットについて、記事は、「一品当たりの販売数量が増え、仕入価格が下がる。作業効率が改善され、生産性が向上する」と解説しています。
さらに、「イオン以外の総合スーパーや百貨店でも過去、何度も叫ばれてきた。だが、思うようには進んでいない」とも指摘しています。要因として、バイヤーの縄張り意識などが挙げられています。
バイヤーには、会社の方針とは別の論理が働いているわけですね。「立場が変われば視点も変わる」とは、このようなことでしょう。だからこそ、それを超越した「トップの裁量」が必要となるわけです。
これは、検事や弁護士が裁判官を兼務しないのと同じことです。兼任させておきながら判決結果を批判しても、どうにもなりません。仕組みを変えなくてはならないのですから。
記事はその点について、バイヤー数を減らすことと、「売上高だけでなく粗利(または営業利益)でも管理することが肝心だ」と指摘しています。これは、バイヤーの視点を変える方策だと言えるでしょう。
視点が変われば、行動が変わります。今まで見えていなかったものが見えるようになり、それが「気づき」を生むからです。「気づき」を得ずして、人はなかなか、行動を改めるものではありません。
「トップの裁量」は、どこに視点を向けよ、と示すことに発揮されます。品目数の削減は「結果」に過ぎず、それを達成するために必要なのは、その結果に至るプロセスを変えることであり、それには視点の移動が必要だからなのです。
【今日の教訓】
あなたは経営者として、自社の従業員の視点をどこに導いているだろうか。今までとは異なる方針を徹底したいと思うのなら、視点を変えることを促す必要がある。それを実現するために、経営者としてのリーダーシップを発揮しよう。
<参考:日経MJ(流通新聞) 2009.04.06【3面】>
2009年04月02日
まずはセルフイメージを変えること。
売上を拡大するために、新規事業の開発・立ち上げや、新商品の投入に積極的に取り組む企業は多いですね。その際、自社を俯瞰して眺めてみるとよいと思います。
要は、自社はいったい「何屋」なのか、という話です。目先の売上を追求し、がむしゃらに新規事業・新商品への取り組みを進めていくと、自社はいったい「何屋」なのか、わからなくなってきたりします。
逆に、自社が「何屋」であるかを先に定義し、その上で、だからこのような事業を立ち上げ、商品をリリースする必要がある、と考えていく企業もあります。
後者のような経営の方が、より戦略的と言えるわけですが、前者のようなやり方でも、取り組みを進めていくにつれ、「定義」の必要性に目覚めていくことになります。
4月2日付けの日本経済新聞に、「都内タクシー中堅のANZENGroupは4月、タクシーで生活支援サービス事業に参入する」という記事が掲載されています。
具体的には、「乗務員が消費者の用事を代行する9種類の『サービスタクシー』を始める」のだそうです。記事は、例として、病院の予約代行、薬の代理受け取り、高齢者の安否確認といったサービスを紹介しています。
背景には「都内のタクシーの利用離れ」があり、「競争が激しいため、新サービスで差異化を狙う」意図に基づきます。単純な新規事業というより、タクシー会社とは「何屋」なのか、その定義まで踏み込む取り組みとして受け止める必要がありそうです。
記事によれば、「こうした支援サービスを展開するタクシー会社は郊外や地方がほとんどだった」そうです。都内のタクシー会社もそれらを手掛けるとなると、タクシーというもののイメージも、大きく変わってくるでしょう。
タクシーを、運送業ではなくサービス業ととらえ、業界に新風を巻き起こしたタクシー会社がありました。これも「定義」の変更に相当しますが、ビジネスモデルそのものが変わるわけではありません。
「生活支援サービス業」として運賃以外の収益を獲得するようになれば、それはビジネスモデルそのものの変革になります。昔ながらのタクシーのイメージとは、大きく異なります。
変化に対応し、自らも変わらなければ、生き残れない。よく言われることです。きっかけは、景気や時流といった外的要因かも知れませんが、変革の真の原動力は、自社の事業領域を「再定義」することにある。
個人レベルで言えば、「セルフイメージ」を変えるということになるだでしょうか。セルフイメージが変われば、どのように行動を変えるべきかも、わかってきます。
このような変革は、実は至るところで起きています。たとえば本日付けの日経によれば、文部科学省は、図書館司書の養成課程を大幅に見直し、「ネット時代の図書館司書を育てる」ことに取り組むのだそうです。背景として、タクシーと同様、図書館の役割の変革があります。
※2009年4月2日付け日本経済新聞朝刊34面より
新規事業や新商品・新サービスを生む源泉は、本来、自社事業の定義、ひいてはセルフイメージにあります。アイデアが出ないとすれば、旧来のセルフイメージにとらわれているからかも知れません。
【今日の教訓】
あなたの企業は、どのようなセルフイメージを持っているだろうか。そのイメージは、時代の変化に耐え得るものだろうか。新たなセルフイメージを確立すれば、時流に乗った、さまざまな事業・商品・サービスを生み出す原動力となる。自社はいったい「何屋」なのか、再定義することから始めてみよう。
<参考:日本経済新聞 2009.04.02【10面】>
要は、自社はいったい「何屋」なのか、という話です。目先の売上を追求し、がむしゃらに新規事業・新商品への取り組みを進めていくと、自社はいったい「何屋」なのか、わからなくなってきたりします。
逆に、自社が「何屋」であるかを先に定義し、その上で、だからこのような事業を立ち上げ、商品をリリースする必要がある、と考えていく企業もあります。
後者のような経営の方が、より戦略的と言えるわけですが、前者のようなやり方でも、取り組みを進めていくにつれ、「定義」の必要性に目覚めていくことになります。
4月2日付けの日本経済新聞に、「都内タクシー中堅のANZENGroupは4月、タクシーで生活支援サービス事業に参入する」という記事が掲載されています。
具体的には、「乗務員が消費者の用事を代行する9種類の『サービスタクシー』を始める」のだそうです。記事は、例として、病院の予約代行、薬の代理受け取り、高齢者の安否確認といったサービスを紹介しています。
背景には「都内のタクシーの利用離れ」があり、「競争が激しいため、新サービスで差異化を狙う」意図に基づきます。単純な新規事業というより、タクシー会社とは「何屋」なのか、その定義まで踏み込む取り組みとして受け止める必要がありそうです。
記事によれば、「こうした支援サービスを展開するタクシー会社は郊外や地方がほとんどだった」そうです。都内のタクシー会社もそれらを手掛けるとなると、タクシーというもののイメージも、大きく変わってくるでしょう。
タクシーを、運送業ではなくサービス業ととらえ、業界に新風を巻き起こしたタクシー会社がありました。これも「定義」の変更に相当しますが、ビジネスモデルそのものが変わるわけではありません。
「生活支援サービス業」として運賃以外の収益を獲得するようになれば、それはビジネスモデルそのものの変革になります。昔ながらのタクシーのイメージとは、大きく異なります。
変化に対応し、自らも変わらなければ、生き残れない。よく言われることです。きっかけは、景気や時流といった外的要因かも知れませんが、変革の真の原動力は、自社の事業領域を「再定義」することにある。
個人レベルで言えば、「セルフイメージ」を変えるということになるだでしょうか。セルフイメージが変われば、どのように行動を変えるべきかも、わかってきます。
このような変革は、実は至るところで起きています。たとえば本日付けの日経によれば、文部科学省は、図書館司書の養成課程を大幅に見直し、「ネット時代の図書館司書を育てる」ことに取り組むのだそうです。背景として、タクシーと同様、図書館の役割の変革があります。
※2009年4月2日付け日本経済新聞朝刊34面より
新規事業や新商品・新サービスを生む源泉は、本来、自社事業の定義、ひいてはセルフイメージにあります。アイデアが出ないとすれば、旧来のセルフイメージにとらわれているからかも知れません。
【今日の教訓】
あなたの企業は、どのようなセルフイメージを持っているだろうか。そのイメージは、時代の変化に耐え得るものだろうか。新たなセルフイメージを確立すれば、時流に乗った、さまざまな事業・商品・サービスを生み出す原動力となる。自社はいったい「何屋」なのか、再定義することから始めてみよう。
<参考:日本経済新聞 2009.04.02【10面】>
2009年04月02日
レバレッジを効かせるマーケティング
人口が増えない、むしろ減少する時代にあっては、顧客数の増加は期待しにくくなります。となると顧客単価を上昇させる仕組みをつくりたいところです。
顧客との付き合い方は、特定商品の購買という「点」ではなく、生涯にわたり連続的に購買を促す「線」の状態にすることが必要です。さらに、口コミを起こして「面」にまで出来れば理想的です。
「線」を志向する場合は、出来る限り長く引っ張りたいものです。そのためには、「起点」をなるべく早い時期に押さえることが重要となります。「線」の長さは無限ではありません。
具体的に言えば、顧客が消費者だとすれば、なるべく若い時期に顧客化し、生涯にわたり、商品を購買してもらうようにします。企業相手なら、設立当初から付き合い、企業規模の拡大に伴い、取引規模も大きくしていきたいですね。
4月1日付けの日経MJ(流通新聞)に、ライオンのしわ取りスプレー「スタイルガード」についての記事が掲載されています。「大学4年生など就職活動中の学生を対象にした販促を実施する」のだそうです。
「身だしなみのアドバイスやスタイルガードの情報などを載せた冊子のほか、試供品を配る」とのことです。狙いは、「しわ取りスプレーの便利さを訴え、社会人になっても使い続けてもらえるようにする」ことです。
最初の「刷り込み」が重要ということなのでしょう。日常的にスーツを着始める就職活動の時期を押さえれば、その後、40年程度にわたり顧客になる可能性があるわけです。金額換算で考えれば、販促投資の効果は、極めて大きいとみることができます。
そもそも「スタイルガード」のような商品は、どのように認知されるのでしょうか。テレビCMや店頭販促で目にするのかも知れません。ですが、関心を持たない限り、たとえ目に見えていても、特に気にとめないことでしょう。
その点、就職活動中の学生となれば、身だしなみや印象を気にすることから、関心が高まっていると考えられます。身だしなみをアドバイスする冊子を配るとなれば、熱心に目を通すに違いありません。
「点」ではなく、「線」や「面」での展開が重要だということは、よく指摘されることです。「線」で展開するのなら、「起点」を押さえることです。「起点」を押さえれば、「線」を長く押さえることができ、結果として「面」の最大化も期待できます。
「起点」を押さえることは、主導権を握ることにもつながります。ビジネスでは「上流」を押さえよと言われることがよくありますが、「上流」の行き着く先は、まさに「起点」です。
資源の重点配分の点でも、「起点」を押さえるのは賢明です。先述のように、40年にわたって効果が持続するのなら、最大限のレバレッジを効かせることができるからです。
顧客ターゲットをどう設定するかは、マーケティング上の重要なテーマです。選定基準の一つとして、線の「起点」を狙うという観点は、欠かせませんね。
【今日の教訓】
あなたの企業では、顧客ターゲットをどのように設定しているだろうか。「線」そして「面」での付き合いをしていくことが求められているとすれば、最大のレバレッジを得られる「起点」を狙うことを忘れてはならない。
<参考:日経MJ(流通新聞) 2009.04.01【6面】>
顧客との付き合い方は、特定商品の購買という「点」ではなく、生涯にわたり連続的に購買を促す「線」の状態にすることが必要です。さらに、口コミを起こして「面」にまで出来れば理想的です。
「線」を志向する場合は、出来る限り長く引っ張りたいものです。そのためには、「起点」をなるべく早い時期に押さえることが重要となります。「線」の長さは無限ではありません。
具体的に言えば、顧客が消費者だとすれば、なるべく若い時期に顧客化し、生涯にわたり、商品を購買してもらうようにします。企業相手なら、設立当初から付き合い、企業規模の拡大に伴い、取引規模も大きくしていきたいですね。
4月1日付けの日経MJ(流通新聞)に、ライオンのしわ取りスプレー「スタイルガード」についての記事が掲載されています。「大学4年生など就職活動中の学生を対象にした販促を実施する」のだそうです。
「身だしなみのアドバイスやスタイルガードの情報などを載せた冊子のほか、試供品を配る」とのことです。狙いは、「しわ取りスプレーの便利さを訴え、社会人になっても使い続けてもらえるようにする」ことです。
最初の「刷り込み」が重要ということなのでしょう。日常的にスーツを着始める就職活動の時期を押さえれば、その後、40年程度にわたり顧客になる可能性があるわけです。金額換算で考えれば、販促投資の効果は、極めて大きいとみることができます。
そもそも「スタイルガード」のような商品は、どのように認知されるのでしょうか。テレビCMや店頭販促で目にするのかも知れません。ですが、関心を持たない限り、たとえ目に見えていても、特に気にとめないことでしょう。
その点、就職活動中の学生となれば、身だしなみや印象を気にすることから、関心が高まっていると考えられます。身だしなみをアドバイスする冊子を配るとなれば、熱心に目を通すに違いありません。
「点」ではなく、「線」や「面」での展開が重要だということは、よく指摘されることです。「線」で展開するのなら、「起点」を押さえることです。「起点」を押さえれば、「線」を長く押さえることができ、結果として「面」の最大化も期待できます。
「起点」を押さえることは、主導権を握ることにもつながります。ビジネスでは「上流」を押さえよと言われることがよくありますが、「上流」の行き着く先は、まさに「起点」です。
資源の重点配分の点でも、「起点」を押さえるのは賢明です。先述のように、40年にわたって効果が持続するのなら、最大限のレバレッジを効かせることができるからです。
顧客ターゲットをどう設定するかは、マーケティング上の重要なテーマです。選定基準の一つとして、線の「起点」を狙うという観点は、欠かせませんね。
【今日の教訓】
あなたの企業では、顧客ターゲットをどのように設定しているだろうか。「線」そして「面」での付き合いをしていくことが求められているとすれば、最大のレバレッジを得られる「起点」を狙うことを忘れてはならない。
<参考:日経MJ(流通新聞) 2009.04.01【6面】>
2009年03月30日
不況の時期だからこそ、すべきこととは?
100年に一度と言われる不況に見舞われたら、どうすべきでしょうか? いろいろと手を尽くそうとする企業がある一方で、むしろ何もするなという姿勢の企業もあります。
無理に売上をつくるためにジタバタと動いても、成果は上がりません。出張や販促費など、使うだけムダだと考えるわけです。「一人相撲」を取っても仕方がありません。
一方、この不況の機会に、繁忙期になかなか出来なかったことに取り組もうという企業もあります。具体的には、教育研修に時間を使おうと考える企業です。
3月30日付けの日本経済新聞に、富士重工業が「余った時間を使って、社員教育を始めた」という記事が掲載されています。この記事は、「出口の見えない販売不振にあえぐ自動車業界」という文章で始まっています。
社員教育には、時間も費用もかかるというのが「常識」かも知れませんが、富士重工業の場合、「講師役は同僚のボランティア」で、「サークル感覚の勉強会」です。
記事で取り上げられているのは「英文法レベルアップ講座」。2年間の渡米経験があり、TOEICで満点をことのある社員が講師を務める。「予想の2倍以上の応募が殺到」したそうです。
この勉強会は、「沈滞ムードの払拭にも一役買っている」とのことです。「会社の研修」ではなく、「同志が自己啓蒙のために集まる場」なのだそうです。
企業側の視点に立てば、社員に必要なスキルを習得させることが研修の目的となります。ですが、「沈滞ムードの払拭」「同志」といった言葉をみると、それ以上の価値があるように思います。
今回の記事のような、自発的かつ相互扶助的な勉強会なら、なおさらでしょう。スキルの習得にとどまらない、チームビルディング等の効果も見逃してはなりません。
アーネスト・ゴードン著「クワイ河収容所」では、日本軍に捕らわれた英国軍捕虜が、収容所内で秘密の「大学」を開講し、勉強をすることで、自らの尊厳や希望を取り戻したというエピソードが語られています。
勉強をすれば、進歩が実感できます。同僚同士で教え、教えられることで、信頼関係も醸成されます。不況による業績低迷や閉塞感はどうすることもできないとしても、それらは自助努力により成し遂げることができるのです。
個人としての自分の体験を振り返っても、行き詰まった時は、ひたすら勉強することで活路を見出してきたように思います。知識をインプットすることで、視野が広がったということなのでしょうか。
また、誰かと会って刺激を受けるというのも、行き詰まりを打開するのに効果的です。記事の勉強会では、いつもと違う同僚の姿に触れることができるのでしょう。それもまた刺激的です。
行き詰まったら、勉強をするに限ります。個人も企業も、それは同じことなのかも知れません。勉強して知識やスキルを習得すること自体、身を助けますが、それ以上の効能もあるのです。
【今日の教訓】
この不況の時期、閉塞感から脱するために、あなたは何をしているだろうか。勉強をしたり、人と会って刺激を受けることは、非常に効果的だ。個人レベルだけでなく、組織・企業レベルでも、それを行なうことを考えてみよう。
<参考:日本経済新聞 2009.03.30【11面】>
無理に売上をつくるためにジタバタと動いても、成果は上がりません。出張や販促費など、使うだけムダだと考えるわけです。「一人相撲」を取っても仕方がありません。
一方、この不況の機会に、繁忙期になかなか出来なかったことに取り組もうという企業もあります。具体的には、教育研修に時間を使おうと考える企業です。
3月30日付けの日本経済新聞に、富士重工業が「余った時間を使って、社員教育を始めた」という記事が掲載されています。この記事は、「出口の見えない販売不振にあえぐ自動車業界」という文章で始まっています。
社員教育には、時間も費用もかかるというのが「常識」かも知れませんが、富士重工業の場合、「講師役は同僚のボランティア」で、「サークル感覚の勉強会」です。
記事で取り上げられているのは「英文法レベルアップ講座」。2年間の渡米経験があり、TOEICで満点をことのある社員が講師を務める。「予想の2倍以上の応募が殺到」したそうです。
この勉強会は、「沈滞ムードの払拭にも一役買っている」とのことです。「会社の研修」ではなく、「同志が自己啓蒙のために集まる場」なのだそうです。
企業側の視点に立てば、社員に必要なスキルを習得させることが研修の目的となります。ですが、「沈滞ムードの払拭」「同志」といった言葉をみると、それ以上の価値があるように思います。
今回の記事のような、自発的かつ相互扶助的な勉強会なら、なおさらでしょう。スキルの習得にとどまらない、チームビルディング等の効果も見逃してはなりません。
アーネスト・ゴードン著「クワイ河収容所」では、日本軍に捕らわれた英国軍捕虜が、収容所内で秘密の「大学」を開講し、勉強をすることで、自らの尊厳や希望を取り戻したというエピソードが語られています。
勉強をすれば、進歩が実感できます。同僚同士で教え、教えられることで、信頼関係も醸成されます。不況による業績低迷や閉塞感はどうすることもできないとしても、それらは自助努力により成し遂げることができるのです。
個人としての自分の体験を振り返っても、行き詰まった時は、ひたすら勉強することで活路を見出してきたように思います。知識をインプットすることで、視野が広がったということなのでしょうか。
また、誰かと会って刺激を受けるというのも、行き詰まりを打開するのに効果的です。記事の勉強会では、いつもと違う同僚の姿に触れることができるのでしょう。それもまた刺激的です。
行き詰まったら、勉強をするに限ります。個人も企業も、それは同じことなのかも知れません。勉強して知識やスキルを習得すること自体、身を助けますが、それ以上の効能もあるのです。
【今日の教訓】
この不況の時期、閉塞感から脱するために、あなたは何をしているだろうか。勉強をしたり、人と会って刺激を受けることは、非常に効果的だ。個人レベルだけでなく、組織・企業レベルでも、それを行なうことを考えてみよう。
<参考:日本経済新聞 2009.03.30【11面】>
2009年03月26日
ネットで展開しているものをリアルに置き換えるという発想
私を育ててくれた先輩コンサルタントから、「物の考え方」と「手順」が重要だということを、何度も教えられました。いきなり「手段・方法」を考えてはいけない、というわけです。
まずはどのような「考え方」で物事に当たるかを決めることが大切です。それが決まれば、どのような「手段・方法」が適切か、答えは自ずと決まってきます。
事業展開については、「手順」が重要だと言えます。後先を間違えると失敗します。「物の考え方」を踏まえた上で、どの「手順」がベストなのか、じっくり考える必要があります。
3月26日付けの日経産業新聞に、「健康機器大手のタニタは健康支援サービス『からだカルテ』の対象者を拡大する」という記事が掲載されています。
「4月から他社製を含むすべての体組成計や歩数計を使えるようにするほか、インターネット以外の通信手段も取り入れる」とのことです。意図は、「高齢者ら日ごろネットに接しない人でも参加できる体制を整え、会員数を早期に10万人規模まで引き上げる」ことです。
「からだカルテ」は恐らく、ネットを活用してできる新サービスとして誕生したものなのだと思います。ところが、ネット以外でも利用できるようになります。このような“逆流”現象は、何とも興味深いです。
日経の過去記事を検索すると、「からだカルテ」は、「インターネットなど、通信網を利用した健康支援サービス」という表現で紹介されています。にも関わらず、ネット以外でも利用できるようにするわけです。※参考:2008年7月29日付け日経産業新聞8面
「からだカルテ」のようなサービスは、自社機器の販促目的という見方もできます。にも関わらず、他社製の機器も使えるようにします。記事によれば、背景として、「メタボ健診の受診率はまだ低く、個人向けサービスも伸び悩むため、会員数は数万人にとどまっていた」という認識があります。
日経の過去記事の中には、メタボ以外の層、すなわち「気軽にダイエットに取り組むような若い世代の獲得が遅れ」ていると指摘する記事もみつかります。※参考:2009年2月4日付け日経産業新聞12面
つまり、ネット以外や他社機器による利用については、当初想定していなかったが、利用者獲得の伸び悩みが、そのような施策の転換を促したと考えられるわけです。
もっとも、「からだカルテ」は、それ自体有料サービスなので、とにもかくにも利用者数を増やすことが重要でしょう。となれば、自社機器の販促目的にこだわらなくてよいのです。また、ネットを経由せずとも、利用が不可能なわけでもありません。
とは言え、ネット経由でのサービス提供を行なった実績がなければ、ネット経由以外でそれを提供するという発想は、生まれなかったかも知れません。先ほど“逆流”という表現を使ったように、発想にも「手順」あるいは「順序」があるわけです。
インターネットの普及により、従来は考えられなかったような様々なサービスが誕生しています。しかし考えてみれば、それらの中には、リアルでも展開できるものもあるかも知れません。
たとえば、「この商品を買った人は、この商品も買っています」といった表示は、即時性は実現しないにしても、リアル店舗でも使えそうな販促テクニックです。
リアルのビジネスがネットに置き換えられたり、ネット独自のサービスが生まれたりもしています。ならば、ネット独自のサービスやビジネスをリアルで展開することを考えてもよいのではないでしょうか。
【今日の教訓】
ネットで展開されているビジネスやサービスについて、それらをリアルで展開できないか、考えてみよう。リアルからネットに置き換えられるものがあるのなら、その逆もあり得るはずだ。
<参考:日経産業新聞 2009.03.26【14面】>
まずはどのような「考え方」で物事に当たるかを決めることが大切です。それが決まれば、どのような「手段・方法」が適切か、答えは自ずと決まってきます。
事業展開については、「手順」が重要だと言えます。後先を間違えると失敗します。「物の考え方」を踏まえた上で、どの「手順」がベストなのか、じっくり考える必要があります。
3月26日付けの日経産業新聞に、「健康機器大手のタニタは健康支援サービス『からだカルテ』の対象者を拡大する」という記事が掲載されています。
「4月から他社製を含むすべての体組成計や歩数計を使えるようにするほか、インターネット以外の通信手段も取り入れる」とのことです。意図は、「高齢者ら日ごろネットに接しない人でも参加できる体制を整え、会員数を早期に10万人規模まで引き上げる」ことです。
「からだカルテ」は恐らく、ネットを活用してできる新サービスとして誕生したものなのだと思います。ところが、ネット以外でも利用できるようになります。このような“逆流”現象は、何とも興味深いです。
日経の過去記事を検索すると、「からだカルテ」は、「インターネットなど、通信網を利用した健康支援サービス」という表現で紹介されています。にも関わらず、ネット以外でも利用できるようにするわけです。※参考:2008年7月29日付け日経産業新聞8面
「からだカルテ」のようなサービスは、自社機器の販促目的という見方もできます。にも関わらず、他社製の機器も使えるようにします。記事によれば、背景として、「メタボ健診の受診率はまだ低く、個人向けサービスも伸び悩むため、会員数は数万人にとどまっていた」という認識があります。
日経の過去記事の中には、メタボ以外の層、すなわち「気軽にダイエットに取り組むような若い世代の獲得が遅れ」ていると指摘する記事もみつかります。※参考:2009年2月4日付け日経産業新聞12面
つまり、ネット以外や他社機器による利用については、当初想定していなかったが、利用者獲得の伸び悩みが、そのような施策の転換を促したと考えられるわけです。
もっとも、「からだカルテ」は、それ自体有料サービスなので、とにもかくにも利用者数を増やすことが重要でしょう。となれば、自社機器の販促目的にこだわらなくてよいのです。また、ネットを経由せずとも、利用が不可能なわけでもありません。
とは言え、ネット経由でのサービス提供を行なった実績がなければ、ネット経由以外でそれを提供するという発想は、生まれなかったかも知れません。先ほど“逆流”という表現を使ったように、発想にも「手順」あるいは「順序」があるわけです。
インターネットの普及により、従来は考えられなかったような様々なサービスが誕生しています。しかし考えてみれば、それらの中には、リアルでも展開できるものもあるかも知れません。
たとえば、「この商品を買った人は、この商品も買っています」といった表示は、即時性は実現しないにしても、リアル店舗でも使えそうな販促テクニックです。
リアルのビジネスがネットに置き換えられたり、ネット独自のサービスが生まれたりもしています。ならば、ネット独自のサービスやビジネスをリアルで展開することを考えてもよいのではないでしょうか。
【今日の教訓】
ネットで展開されているビジネスやサービスについて、それらをリアルで展開できないか、考えてみよう。リアルからネットに置き換えられるものがあるのなら、その逆もあり得るはずだ。
<参考:日経産業新聞 2009.03.26【14面】>
タグ :からだカルテ
2009年03月24日
料理人向けの情報サイト「ぐるなびシェフ」
コンサルティングのスタート時は、クライアントのビジネスモデルを徹底的に研究します。どのような仕組みで商品が売れるのか、まずはそれを解明します。
その際は、商品が販売される現場から、さかのぼっていくことがあります。「風が吹けば桶屋が儲かる」を、逆からたどるわけです。それは、顧客の行動や心理を分析することにもつながります。
すると、特定の商品の売れ行きをよくするための「条件」が見えてきたりもします。「将を射んと欲すればまず馬を射よ」という言葉のように、「将」だけでなく「馬」も視野に入れる必要があることに気づいたりします。
3月24日付けの日経産業新聞に、「飲食店検索大手のぐるなびは24日、料理人向けの情報を掲載するサイト『ぐるなびシェフ』を立ち上げる」という記事が掲載されています。
「主に若手や、これから開業を控える料理人を対象に、地方の珍しい食材情報や調理の基礎技術が学べる動画コンテンツなどを掲載」するそうです。
狙いは「シェフに役立つ情報の提供を通じて、飲食店と地方の生産者、ぐるなびの連携を強化する」ことです。ぐるなびのサイトのエンドユーザは、基本的には消費者ですが、今回の取り組みは、シェフをエンドユーザとし、生産者の注目も集めるものです。
ぐるなびの真の顧客は、加盟料等を支払う飲食店であり、シェフが意思決定者となる場合も多いでしょう。とは言え、消費者向けのサイトのエンドユーザではない分、現実的な関係としては、比較的疎遠なように思います。
ですが、ぐるなびシェフが立ち上がることで、シェフとぐるなびの関係は、一挙に近づきますね。加盟店集めのプロモーション策としても、有効に機能するでしょう。記事の「若手や、これから開業を控える料理人を対象に」という記述から、それは明らかです。
「将」と「馬」の関係で言えば、実際に加盟料を払うシェフが「将」で、ぐるなび経由で予約を入れる消費者が「馬」となります。消費者がたくさん利用すればするほど、加盟する魅力が高まるからです。
ぐるなびの場合、加盟店開拓は訪問営業により行なってきたようです。もちろん、ぐるなびのサイトでも、加盟店を募集していますが、基本的には消費者向けサイトなので、訴求は弱いです。だからこそ、訪問営業が必要となるわけですね。
今回の取り組みは、「将」であるシェフに、直接かつ広くアプローチする仕組みとなります。「将を射んと欲すればまず馬を射よ」とは言いますが、直接「将」にアプローチする仕組みが弱いとすれば、それはそれで問題だと言えるでしょう。ぐるなびシェフは、その問題を解決する存在です。いずれにしろ、両面を押さえれば、強いわけです。
また、ぐるなびは、各加盟店をサポートする仕組みが整っていることでも知られています。今回の取り組みは、その一環でもあるでしょう。顧客にとって、なくてはならない存在になる手を、着々と打っているわけですね。
訪問営業で加盟店顧客を集め、手厚いサポートを提供します。さらには、サービス提供の対象を未加盟店にまで広げ、加盟店拡大へと結び付けていく。エンドユーザたる消費者の利用も活発です。
「将を射んと欲すればまず馬を射よ」というのは、言ってみれば「線」を押さえる取り組みです。ぐるなびの今回の取り組みは、「将」も「馬」も、一網打尽に取り込んでしまうような、「面」の施策だと言えるでしょう。
【今日の教訓】
あなたの企業は、自社の商品を拡販するための仕組みを、どのように構築しているだろうか。ロジカルにつながる「線」の仕組みを押さえたら、「面」の施策の構築に取り掛かろう。そうすることで、「顧客にとって、なくてはならない存在」になることができる。
<参考:日経産業新聞 2009.03.24【4面】>
その際は、商品が販売される現場から、さかのぼっていくことがあります。「風が吹けば桶屋が儲かる」を、逆からたどるわけです。それは、顧客の行動や心理を分析することにもつながります。
すると、特定の商品の売れ行きをよくするための「条件」が見えてきたりもします。「将を射んと欲すればまず馬を射よ」という言葉のように、「将」だけでなく「馬」も視野に入れる必要があることに気づいたりします。
3月24日付けの日経産業新聞に、「飲食店検索大手のぐるなびは24日、料理人向けの情報を掲載するサイト『ぐるなびシェフ』を立ち上げる」という記事が掲載されています。
「主に若手や、これから開業を控える料理人を対象に、地方の珍しい食材情報や調理の基礎技術が学べる動画コンテンツなどを掲載」するそうです。
狙いは「シェフに役立つ情報の提供を通じて、飲食店と地方の生産者、ぐるなびの連携を強化する」ことです。ぐるなびのサイトのエンドユーザは、基本的には消費者ですが、今回の取り組みは、シェフをエンドユーザとし、生産者の注目も集めるものです。
ぐるなびの真の顧客は、加盟料等を支払う飲食店であり、シェフが意思決定者となる場合も多いでしょう。とは言え、消費者向けのサイトのエンドユーザではない分、現実的な関係としては、比較的疎遠なように思います。
ですが、ぐるなびシェフが立ち上がることで、シェフとぐるなびの関係は、一挙に近づきますね。加盟店集めのプロモーション策としても、有効に機能するでしょう。記事の「若手や、これから開業を控える料理人を対象に」という記述から、それは明らかです。
「将」と「馬」の関係で言えば、実際に加盟料を払うシェフが「将」で、ぐるなび経由で予約を入れる消費者が「馬」となります。消費者がたくさん利用すればするほど、加盟する魅力が高まるからです。
ぐるなびの場合、加盟店開拓は訪問営業により行なってきたようです。もちろん、ぐるなびのサイトでも、加盟店を募集していますが、基本的には消費者向けサイトなので、訴求は弱いです。だからこそ、訪問営業が必要となるわけですね。
今回の取り組みは、「将」であるシェフに、直接かつ広くアプローチする仕組みとなります。「将を射んと欲すればまず馬を射よ」とは言いますが、直接「将」にアプローチする仕組みが弱いとすれば、それはそれで問題だと言えるでしょう。ぐるなびシェフは、その問題を解決する存在です。いずれにしろ、両面を押さえれば、強いわけです。
また、ぐるなびは、各加盟店をサポートする仕組みが整っていることでも知られています。今回の取り組みは、その一環でもあるでしょう。顧客にとって、なくてはならない存在になる手を、着々と打っているわけですね。
訪問営業で加盟店顧客を集め、手厚いサポートを提供します。さらには、サービス提供の対象を未加盟店にまで広げ、加盟店拡大へと結び付けていく。エンドユーザたる消費者の利用も活発です。
「将を射んと欲すればまず馬を射よ」というのは、言ってみれば「線」を押さえる取り組みです。ぐるなびの今回の取り組みは、「将」も「馬」も、一網打尽に取り込んでしまうような、「面」の施策だと言えるでしょう。
【今日の教訓】
あなたの企業は、自社の商品を拡販するための仕組みを、どのように構築しているだろうか。ロジカルにつながる「線」の仕組みを押さえたら、「面」の施策の構築に取り掛かろう。そうすることで、「顧客にとって、なくてはならない存在」になることができる。
<参考:日経産業新聞 2009.03.24【4面】>
2009年03月17日
新規事業を発想する4つの切り口とは?
先日、ドリームゲートのセミナー(チャレンジゲート)で、起業ネタの発想法に関するレクチャーを行ないました。基本はまず、専門分野を決めること。ここを起点にネタを発想していくことをお話ししました。
これは、企業が新規事業のアイデアを発想する際のノウハウを流用したものです。起業を目指す個人向けには「専門分野」という用語を使いますが、企業なら「事業ドメイン(領域)」に相当します。
「専門分野」「事業ドメイン」を決めた上で、「モノ」「ワザ・スキル」「知識・情報」「場・ネットワーク」の4つの切り口で、どのような商品を売ることができるかを考えます。
既に自社のドメインで「モノ」を売っているのなら、それに関する「知識・情報」を売ることが、新規事業になります。もちろん、その逆もあり得ます。
3月17日付けの日本経済新聞に、「オムロンは工場の消費電力削減を支援する環境コンサルティング事業に本格参入する」という記事が掲載されています。
記事によれば、「自社の電力センサーや制御機器を販売、電力の削減方法を指南する」そうです。具体的には、「消費電力の削減余地を調べて、自社の工場で培った省エネルギー化のノウハウを提供」していくとのことです。
センサーや制御機器という「モノ」を売るビジネスに、コンサルティングという「知識・情報」を売るビジネスを付加するというわけでうs。コンサルティング事業では、「2013年度に100億円の売り上げを目指す」というからたいした規模です。
オムロンのそもそものビジネスは機器類の製造・販売ですから、コンサルティングは、新規事業になります。しかし、記事を読む限りでは、実際の販売は、その逆です。
つまり、省エネルギー化のノウハウ提供というコンサルティングを売り込み、それに付随して、「無駄な電力を減らせる蓄電装置や、必要な機械だけを動かせる制御機器などを販売する」ことになります。
新規事業の理想の姿として、既存事業と相乗効果があることが挙げられますが、まさにそのような状況となるわけです。コンサルティングが、機器の需要を創造することにつながっているのです。
電力会社などが省エネルギーのコンサルティングを行なう場合、コンサルティングの成果がメイン商品の需要を減らすことになります。そのような場合、他のエネルギーへの代替防止とはなっても、相乗効果とまでは言い難いでしょう。
いずれにしろ、先述の「4つの切り口」で考えることで、新規事業を生み出し、うまく相乗効果を生むことも可能となります。使い勝手のよいフレームワークだと思います。
具体的なやり方としては、既存事業が確立している場合、それが「4つの切り口」のうちのどれに該当するかを考えてみます。その上で、他の3つの切り口で、どのような商品を売ることができるかを考えてみます。
オムロンの場合、既に「モノ」を売っているので、それと関連した「知識・情報」を売るコンサルティングが新規事業となりました。「省エネルギー」という領域であれば、「ワザ・スキル(代行)」や「場・ネットワーク(マッチングビジネスなど)」も、新規事業となる可能性があるかも知れませんね。
【今日の教訓】
あなたの企業では、自社の新規事業のアイデアを、どのように生みだしているだろうか。自社の事業ドメインを定義し、「モノ」「ワザ・スキル」「知識・情報」「場・ネットワーク」の4つの切り口、で、どのような商品を売ることができるか、考えてみよう。
<参考:日本経済新聞 2009.03.17【11面】>
これは、企業が新規事業のアイデアを発想する際のノウハウを流用したものです。起業を目指す個人向けには「専門分野」という用語を使いますが、企業なら「事業ドメイン(領域)」に相当します。
「専門分野」「事業ドメイン」を決めた上で、「モノ」「ワザ・スキル」「知識・情報」「場・ネットワーク」の4つの切り口で、どのような商品を売ることができるかを考えます。
既に自社のドメインで「モノ」を売っているのなら、それに関する「知識・情報」を売ることが、新規事業になります。もちろん、その逆もあり得ます。
3月17日付けの日本経済新聞に、「オムロンは工場の消費電力削減を支援する環境コンサルティング事業に本格参入する」という記事が掲載されています。
記事によれば、「自社の電力センサーや制御機器を販売、電力の削減方法を指南する」そうです。具体的には、「消費電力の削減余地を調べて、自社の工場で培った省エネルギー化のノウハウを提供」していくとのことです。
センサーや制御機器という「モノ」を売るビジネスに、コンサルティングという「知識・情報」を売るビジネスを付加するというわけでうs。コンサルティング事業では、「2013年度に100億円の売り上げを目指す」というからたいした規模です。
オムロンのそもそものビジネスは機器類の製造・販売ですから、コンサルティングは、新規事業になります。しかし、記事を読む限りでは、実際の販売は、その逆です。
つまり、省エネルギー化のノウハウ提供というコンサルティングを売り込み、それに付随して、「無駄な電力を減らせる蓄電装置や、必要な機械だけを動かせる制御機器などを販売する」ことになります。
新規事業の理想の姿として、既存事業と相乗効果があることが挙げられますが、まさにそのような状況となるわけです。コンサルティングが、機器の需要を創造することにつながっているのです。
電力会社などが省エネルギーのコンサルティングを行なう場合、コンサルティングの成果がメイン商品の需要を減らすことになります。そのような場合、他のエネルギーへの代替防止とはなっても、相乗効果とまでは言い難いでしょう。
いずれにしろ、先述の「4つの切り口」で考えることで、新規事業を生み出し、うまく相乗効果を生むことも可能となります。使い勝手のよいフレームワークだと思います。
具体的なやり方としては、既存事業が確立している場合、それが「4つの切り口」のうちのどれに該当するかを考えてみます。その上で、他の3つの切り口で、どのような商品を売ることができるかを考えてみます。
オムロンの場合、既に「モノ」を売っているので、それと関連した「知識・情報」を売るコンサルティングが新規事業となりました。「省エネルギー」という領域であれば、「ワザ・スキル(代行)」や「場・ネットワーク(マッチングビジネスなど)」も、新規事業となる可能性があるかも知れませんね。
【今日の教訓】
あなたの企業では、自社の新規事業のアイデアを、どのように生みだしているだろうか。自社の事業ドメインを定義し、「モノ」「ワザ・スキル」「知識・情報」「場・ネットワーク」の4つの切り口、で、どのような商品を売ることができるか、考えてみよう。
<参考:日本経済新聞 2009.03.17【11面】>
2009年03月10日
12,000円のソウル行きパッケージ旅行!
物品の整理整頓のコツは、それぞれの定位置を決めておくことだそうです。使い終わったらも、元の場所にきちんと戻す。簡単なようで、意外と出来ていなかったりします。
定位置に納めておかないものは、漂流を続け、挙句の果ては紛失したり。もったいないことですね。また、探す手間が仕事の生産性を下げるとも、よく言われます。
これをビジネスに結びつけて考えると、消費の「定位置」をいかに確保することが大事だということに気づきます。つまり、顧客の財布の中身の一定部分を、確実かつ継続的に取り込めるような商品・サービスを提供することです。
「定位置」を確保できていないと、物品と同様、「漂流を続け、挙句の果ては紛失したり」といったことになります。つまり、せっかくの消費を自社の収益にすることができなくなるわけです。やはり、もったいないことですね。
3月10日付けの日本経済新聞に、「エイチ・アイ・エス(HIS)は9日、料金を12,000円(燃油サーチャージ込み)に抑えた韓国・ソウル行きパッケージ旅行を14日に発売すると発表した」という記事が掲載されています。
12,000円とは、かなりの激安価格です。この金額は、例の「定額給付金」に由来します。さすがにこの価格では厳しいようで、「先着200人の限定商品」となるようではありますが。
言ってみれば「便乗」なのですが、ともすれば「漂流」してしまいそうな給付金を取り込むために、明確な「定位置」を提案するのは、一定の効果がありそうです。
この旅行商品の名称は、ズバリ「定額給付金で行く!ソウル3日間」。「きっと誰かがやるだろう」と思っていたので、さほど驚くことはありません。(当社も何かできないかと考えていたくらいです)
試しに「定額給付金 旅行」で検索すると、日本航空やJTB、近畿日本ツーリスト、さらには各観光地でも、給付金を当て込んだ企画や商品が次々と登場しています。
旅行業界だけではありません。百貨店などでも、給付金を意識したセールが企画されています。貯蓄に回り、景気刺激効果は薄いのではないかと懸念されていた給付金だが、そうでもなさそうです。民間の活力と言うべきでしょうか。
何か一つのことが起きれば、さらに別の何かが誘発されます。戦略を考えるのなら、自社の打ち手がどのように環境に影響するかを考えなければなりません。常に事態は変化するのですから。
定額給付金についても、それだけをとらえれば、将来への不安を抱えている現在、貯蓄に回るだけだという判断になります。しかし、そう単純ではありません。今回の記事では、見事に企業が反応しています。
漠然と貯蓄に回そうと考えていた人も、購買意欲をそそるような「定額給付金キャンペーン」の類を目にすれば、消費の誘惑に負ける確率は高いでしょう。こんなセールや特売があると聞けば、定額給付金に対する印象も変わります。
将棋で最も大切なルールは、交互に打つことだそうです。ヘボな指し手は、相手の反撃があることを忘れて打ち、負けます。要は、一つの物事が引き起こす影響を、つい見逃してしまうということです。
経営において、環境変化を予測することは欠かせません。それを予測し、手を打ったつもりでも、自社の打ち手がもたらす市場やライバルの反応までは考えていなかったりします。愚かなことだが、よくあることでもあります。
【今日の教訓】
あなたは、自社の戦略の推進にあたり、市場やライバル等がどのように反応するか、しっかり予測しているだろうか。プレイヤーは、あなたの企業だけではないのだ。
<参考:日本経済新聞 2009.03.10【9面】>
定位置に納めておかないものは、漂流を続け、挙句の果ては紛失したり。もったいないことですね。また、探す手間が仕事の生産性を下げるとも、よく言われます。
これをビジネスに結びつけて考えると、消費の「定位置」をいかに確保することが大事だということに気づきます。つまり、顧客の財布の中身の一定部分を、確実かつ継続的に取り込めるような商品・サービスを提供することです。
「定位置」を確保できていないと、物品と同様、「漂流を続け、挙句の果ては紛失したり」といったことになります。つまり、せっかくの消費を自社の収益にすることができなくなるわけです。やはり、もったいないことですね。
3月10日付けの日本経済新聞に、「エイチ・アイ・エス(HIS)は9日、料金を12,000円(燃油サーチャージ込み)に抑えた韓国・ソウル行きパッケージ旅行を14日に発売すると発表した」という記事が掲載されています。
12,000円とは、かなりの激安価格です。この金額は、例の「定額給付金」に由来します。さすがにこの価格では厳しいようで、「先着200人の限定商品」となるようではありますが。
言ってみれば「便乗」なのですが、ともすれば「漂流」してしまいそうな給付金を取り込むために、明確な「定位置」を提案するのは、一定の効果がありそうです。
この旅行商品の名称は、ズバリ「定額給付金で行く!ソウル3日間」。「きっと誰かがやるだろう」と思っていたので、さほど驚くことはありません。(当社も何かできないかと考えていたくらいです)
試しに「定額給付金 旅行」で検索すると、日本航空やJTB、近畿日本ツーリスト、さらには各観光地でも、給付金を当て込んだ企画や商品が次々と登場しています。
旅行業界だけではありません。百貨店などでも、給付金を意識したセールが企画されています。貯蓄に回り、景気刺激効果は薄いのではないかと懸念されていた給付金だが、そうでもなさそうです。民間の活力と言うべきでしょうか。
何か一つのことが起きれば、さらに別の何かが誘発されます。戦略を考えるのなら、自社の打ち手がどのように環境に影響するかを考えなければなりません。常に事態は変化するのですから。
定額給付金についても、それだけをとらえれば、将来への不安を抱えている現在、貯蓄に回るだけだという判断になります。しかし、そう単純ではありません。今回の記事では、見事に企業が反応しています。
漠然と貯蓄に回そうと考えていた人も、購買意欲をそそるような「定額給付金キャンペーン」の類を目にすれば、消費の誘惑に負ける確率は高いでしょう。こんなセールや特売があると聞けば、定額給付金に対する印象も変わります。
将棋で最も大切なルールは、交互に打つことだそうです。ヘボな指し手は、相手の反撃があることを忘れて打ち、負けます。要は、一つの物事が引き起こす影響を、つい見逃してしまうということです。
経営において、環境変化を予測することは欠かせません。それを予測し、手を打ったつもりでも、自社の打ち手がもたらす市場やライバルの反応までは考えていなかったりします。愚かなことだが、よくあることでもあります。
【今日の教訓】
あなたは、自社の戦略の推進にあたり、市場やライバル等がどのように反応するか、しっかり予測しているだろうか。プレイヤーは、あなたの企業だけではないのだ。
<参考:日本経済新聞 2009.03.10【9面】>
タグ :定額給付金
2009年03月05日
「家の履歴書」ってご存知?
事業戦略を考える者としては、今までにない新しいビジネスモデルを創造し、成功させることは、常に願っている「夢」となります。新たなビジネスモデルの登場には、新聞も注目し、記事として取り上げてくれます。
昨日のブログでは、デジタル製品の中古買い取りが本格的に始まったという記事を取り上げました。買い取りを前提に新品を販売する仕組みは、新しいビジネスモデルだと言えます。
3月5日付けの日経産業新聞3面は、NECが「ネット経由でソフトの機能を提供する『SaaS(サース)』の新メニューを矢継ぎ早に打ち出している」と伝えています。
売り切りでソフトを販売するのではなく、月額で利用料金を徴収する仕組みにするというのは、ビジネスモデルの転換となります。非常に思い切った決断です。
新しいビジネスモデルの導入や転換は、決して容易なものではありません。それが成り立つ仕組みの構築を十分に考えることが必要です。デジタル製品の中古買い取りにしても、的確に査定ができることや、中古市場の整備が前提となります。
3月5日付けの日本経済新聞に、「住宅大手が設計図や修繕記録などを記した『家の履歴書』の整備に乗り出す」という記事が掲載されています。
これは、中古住宅の流通市場を拡大するための取り組みで、「中古住宅の価格決定を透明に」することが狙いです。住宅販売における新たなビジネスモデルをつくることにつながります。
「新たなビジネスモデル」とは述べましたが、「家の履歴書」という言葉は、今までも何度か目にしたことがあります。日経のデータベースで「家の履歴書」「家歴書」「住宅履歴」と検索すると、既に1999年2月に経済戦略会議が、新たな住宅政策として、住宅履歴簿の必
要性を提言しています。
それからしばらく期間をおいて、福田内閣の掲げた「200年住宅構想」にて「住宅履歴書の整備」が提言されています。それに関連し、住宅大手が「履歴情報の蓄積・管理の仕組みを整備」し始めている一方、「制度的裏付けが足りず業界全体を巻き込んだ動きにはまだなっていない」と日経は伝えています。
2008年3月になると、北海道での事例として、「住まいル・アルバム」という名の「家の履歴書」が、「徐々に広がりはじめた」という記事が掲載されています。2008年12月には「長期優良住宅普及促進法」が成立し、履歴の保存が義務化されました。
そして今回、住宅大手のほか、設備メーカーでも履歴整備を進める動きが伝えられています。「業界全体を巻き込んだ動き」が、ようやく始まった感があります。
住宅履歴の作成が住宅購入者への標準サービスに組み込まれ、一覧できるシステムが開発されるなど、新たなビジネスモデル確立への条件が整ってきました。
随分と時間がかかったと見るべきか、思いのほか短期間で変わったと見るべきか、それはよくわかりません。ですが、単純に「中古住宅市場を活性化しよう」と声をあげただけでは、何も変わらなかったであろうということは、わかります。
「家の履歴書」のように、業界全体を巻き込む必要があるケースはもちろんのこと、一企業としてできるビジネスモデルの転換にしても、条件整備に時間と労力がかかることは多いものです。
2008年3月の記事は、「家歴書」が「余る住宅の活用を促す決め手になるかは不透明だ」と述べていて、このような懐疑的な見方もあるわけです。新たなビジネスモデルの確立は、険しいものだと感じますね。
<情報源:日本経済新聞 2009.03.05【10面】>
※参考:1999年2月27日付け日本経済新聞朝刊4面
:2007年10月10日付け日経産業新聞17面
:2008年3月25日付け日本経済新聞夕刊1面
【今日の教訓】
あなたの企業では、新たなビジネスモデルを確立するために、どのような条件整備作業が必要か、理解しているだろうか。成功を手にするには、それを乗り越えることが求められる。の覚悟で臨もう。
昨日のブログでは、デジタル製品の中古買い取りが本格的に始まったという記事を取り上げました。買い取りを前提に新品を販売する仕組みは、新しいビジネスモデルだと言えます。
3月5日付けの日経産業新聞3面は、NECが「ネット経由でソフトの機能を提供する『SaaS(サース)』の新メニューを矢継ぎ早に打ち出している」と伝えています。
売り切りでソフトを販売するのではなく、月額で利用料金を徴収する仕組みにするというのは、ビジネスモデルの転換となります。非常に思い切った決断です。
新しいビジネスモデルの導入や転換は、決して容易なものではありません。それが成り立つ仕組みの構築を十分に考えることが必要です。デジタル製品の中古買い取りにしても、的確に査定ができることや、中古市場の整備が前提となります。
3月5日付けの日本経済新聞に、「住宅大手が設計図や修繕記録などを記した『家の履歴書』の整備に乗り出す」という記事が掲載されています。
これは、中古住宅の流通市場を拡大するための取り組みで、「中古住宅の価格決定を透明に」することが狙いです。住宅販売における新たなビジネスモデルをつくることにつながります。
「新たなビジネスモデル」とは述べましたが、「家の履歴書」という言葉は、今までも何度か目にしたことがあります。日経のデータベースで「家の履歴書」「家歴書」「住宅履歴」と検索すると、既に1999年2月に経済戦略会議が、新たな住宅政策として、住宅履歴簿の必
要性を提言しています。
それからしばらく期間をおいて、福田内閣の掲げた「200年住宅構想」にて「住宅履歴書の整備」が提言されています。それに関連し、住宅大手が「履歴情報の蓄積・管理の仕組みを整備」し始めている一方、「制度的裏付けが足りず業界全体を巻き込んだ動きにはまだなっていない」と日経は伝えています。
2008年3月になると、北海道での事例として、「住まいル・アルバム」という名の「家の履歴書」が、「徐々に広がりはじめた」という記事が掲載されています。2008年12月には「長期優良住宅普及促進法」が成立し、履歴の保存が義務化されました。
そして今回、住宅大手のほか、設備メーカーでも履歴整備を進める動きが伝えられています。「業界全体を巻き込んだ動き」が、ようやく始まった感があります。
住宅履歴の作成が住宅購入者への標準サービスに組み込まれ、一覧できるシステムが開発されるなど、新たなビジネスモデル確立への条件が整ってきました。
随分と時間がかかったと見るべきか、思いのほか短期間で変わったと見るべきか、それはよくわかりません。ですが、単純に「中古住宅市場を活性化しよう」と声をあげただけでは、何も変わらなかったであろうということは、わかります。
「家の履歴書」のように、業界全体を巻き込む必要があるケースはもちろんのこと、一企業としてできるビジネスモデルの転換にしても、条件整備に時間と労力がかかることは多いものです。
2008年3月の記事は、「家歴書」が「余る住宅の活用を促す決め手になるかは不透明だ」と述べていて、このような懐疑的な見方もあるわけです。新たなビジネスモデルの確立は、険しいものだと感じますね。
<情報源:日本経済新聞 2009.03.05【10面】>
※参考:1999年2月27日付け日本経済新聞朝刊4面
:2007年10月10日付け日経産業新聞17面
:2008年3月25日付け日本経済新聞夕刊1面
【今日の教訓】
あなたの企業では、新たなビジネスモデルを確立するために、どのような条件整備作業が必要か、理解しているだろうか。成功を手にするには、それを乗り越えることが求められる。の覚悟で臨もう。
タグ :家の履歴書
2009年03月04日
ヨドバシカメラがデジタル製品の中古品買い取りを開始
景気の後退は、多くの業種にとって「逆風」ですが、むしろ「追い風」として伸びる業種もありまする。たとえば財布のヒモが堅くなれば、安売り系の業種が伸びます。
このブログで、スキー用具はレンタルの利用者数が大幅に増加している<という記事を取り上げたこともあります。経済合理性の高い消費行動と言えるでしょう。
米国では、P&Gが洗車サービスに参入したそうです。クルマの売れ行きが悪くなっており、消費者の、クルマを長持ちさせようという気持ちを見込んでのことです。
※参考:日経MJ(流通新聞) 2009.03.04【16面】
となると、新品の売れ行きが落ち込むわけですが、それを何とかしようという動きも現れています。2月4日付けの日経MJ(流通新聞)に、
「ヨドバシカメラは、パソコンや携帯音楽プレーヤーなどデジタル製品の中古品買い取りを本格的に始める」という記事が掲載されています。
狙いは、「客が使っている古い製品を買い取ることが、新製品を買うきっかけになる」ことにあります。買い取られた古い製品は、おそらくは中古品として販売されることになるのでしょう。
中古品の流通は、一見、新品の販売の妨げになりますが、実は持ちつ持たれつの関係になっているわけです。これは既に、自動車販売の業界で広く普及している仕組みです。
新車を3年で買い替えることができるのは、中古車の下取りの仕組みがよく整備されているからです。売却時の査定価格次第ですが、買い替えても損をしないことになったりします。
新車ではなく、中古車しか買う気のない客層もいます。最終的には、発展途上国に輸出されたりもするのでしょう。いずれにしろ、商品がうまく流れる仕組みができています。
さらに言えば、車検費用の問題も絡みます。高い車検費用を払うのなら、新車購入後3年での最初の車検の前に下取りに出し、新車に買い替えた方がよいと考えたりします。車検制度がなくなれば、新車の販売台数は落ち込むことでしょうね。
他業界の仕組みをマネし、自業界に採り入れるというは、悪くないです。今回のケースは、自動車販売業界の仕組みをデジタル製品販売業界に採り入れたような格好になります。
しかし、デジタル製品には「車検制度」のようなものはないので、自動車販売と全く同様な効果があるとは言い難いでしょう。中古デジタル製品の購入は、中古車購入ほどは普及もしていませんよね。
とは言え、いわゆる「もったいない」の精神からすれば、中古品のリサイクルの普及は、必要だと思います。最近は、不用なデジタル製品の処分も容易ではなく、その点は、車検制度ほどではありませんが、下取りの促進要因にもなるでしょう。
いずれにしろ、商品の「回転」を促進することは、ビジネスにとって、非常に重要だと認識させられる取り組みです。人口が減少傾向となれば、「回転率」を上げることは、ますます重要になります。
結局のところ、ビジネスは、取り引き(流通)があって、なんぼの世界です。流れのどこかが滞留すれば、ビジネスも停滞します。自動車やデジタル製品販売の業界以外でも、滞留防止の取り組みはみられます。
卑近な例では、飲食店で、食べ終えた料理の皿をどんどん片付けてテーブルを空にすることも、滞留を解消し、新たなオーダーを促進する取り組みだと言えます。
販売先の在庫が滞留しているのなら、それを引き取って、もっと売れる商品を仕入れてもらった方がよいかも知れません。回転率が高ければ、引き取りの費用など、あっという前にペイしてしまうでしょう。いわゆる「損切り」の考え方です。
客先に目を光らせて、「滞留」がないか、チェックしてみてはいかがでしょうか。それを解消する仕組みを編み出せば、販売促進につながるはずです。
【今日の教訓】
あなたの企業の製品は、客先で滞留してはいないだろうか。滞留が解消されれば、回転率が高まり、収益性も上がるはずだ。チェックをし、滞留の解消策を考えてみよう。
<参考:日経MJ(流通新聞) 2009.03.04【7面】>
このブログで、スキー用具はレンタルの利用者数が大幅に増加している<という記事を取り上げたこともあります。経済合理性の高い消費行動と言えるでしょう。
米国では、P&Gが洗車サービスに参入したそうです。クルマの売れ行きが悪くなっており、消費者の、クルマを長持ちさせようという気持ちを見込んでのことです。
※参考:日経MJ(流通新聞) 2009.03.04【16面】
となると、新品の売れ行きが落ち込むわけですが、それを何とかしようという動きも現れています。2月4日付けの日経MJ(流通新聞)に、
「ヨドバシカメラは、パソコンや携帯音楽プレーヤーなどデジタル製品の中古品買い取りを本格的に始める」という記事が掲載されています。
狙いは、「客が使っている古い製品を買い取ることが、新製品を買うきっかけになる」ことにあります。買い取られた古い製品は、おそらくは中古品として販売されることになるのでしょう。
中古品の流通は、一見、新品の販売の妨げになりますが、実は持ちつ持たれつの関係になっているわけです。これは既に、自動車販売の業界で広く普及している仕組みです。
新車を3年で買い替えることができるのは、中古車の下取りの仕組みがよく整備されているからです。売却時の査定価格次第ですが、買い替えても損をしないことになったりします。
新車ではなく、中古車しか買う気のない客層もいます。最終的には、発展途上国に輸出されたりもするのでしょう。いずれにしろ、商品がうまく流れる仕組みができています。
さらに言えば、車検費用の問題も絡みます。高い車検費用を払うのなら、新車購入後3年での最初の車検の前に下取りに出し、新車に買い替えた方がよいと考えたりします。車検制度がなくなれば、新車の販売台数は落ち込むことでしょうね。
他業界の仕組みをマネし、自業界に採り入れるというは、悪くないです。今回のケースは、自動車販売業界の仕組みをデジタル製品販売業界に採り入れたような格好になります。
しかし、デジタル製品には「車検制度」のようなものはないので、自動車販売と全く同様な効果があるとは言い難いでしょう。中古デジタル製品の購入は、中古車購入ほどは普及もしていませんよね。
とは言え、いわゆる「もったいない」の精神からすれば、中古品のリサイクルの普及は、必要だと思います。最近は、不用なデジタル製品の処分も容易ではなく、その点は、車検制度ほどではありませんが、下取りの促進要因にもなるでしょう。
いずれにしろ、商品の「回転」を促進することは、ビジネスにとって、非常に重要だと認識させられる取り組みです。人口が減少傾向となれば、「回転率」を上げることは、ますます重要になります。
結局のところ、ビジネスは、取り引き(流通)があって、なんぼの世界です。流れのどこかが滞留すれば、ビジネスも停滞します。自動車やデジタル製品販売の業界以外でも、滞留防止の取り組みはみられます。
卑近な例では、飲食店で、食べ終えた料理の皿をどんどん片付けてテーブルを空にすることも、滞留を解消し、新たなオーダーを促進する取り組みだと言えます。
販売先の在庫が滞留しているのなら、それを引き取って、もっと売れる商品を仕入れてもらった方がよいかも知れません。回転率が高ければ、引き取りの費用など、あっという前にペイしてしまうでしょう。いわゆる「損切り」の考え方です。
客先に目を光らせて、「滞留」がないか、チェックしてみてはいかがでしょうか。それを解消する仕組みを編み出せば、販売促進につながるはずです。
【今日の教訓】
あなたの企業の製品は、客先で滞留してはいないだろうか。滞留が解消されれば、回転率が高まり、収益性も上がるはずだ。チェックをし、滞留の解消策を考えてみよう。
<参考:日経MJ(流通新聞) 2009.03.04【7面】>
2009年02月23日
ニトリ快進撃の秘密とは?
不況の直撃を受けた企業が何とか生き残りを図るには、どうすることが必要でしょうか。多くの企業では、固定費を削減し、損益分岐点を引き下げることを考えます。
そのようなことは、今まで何度も行なわれてきました。具体的には、人員削減や工場の閉鎖といった取り組みです。やむを得ないことではありますが、それによるダメージもまた、取り沙汰されます。
固定費は、決して「必要悪」なのではありません。収益を稼ぐエンジンのようなものです。エンジンを小さくしてしまえば、当然、収益力などの「出力」が衰えます。それがダメージとなります。
とは言え、エンジンの「燃費」が悪ければ、やはりこのエンジンではマズいということになります。その判断が難しいところですが、それが経営というものでしょう。
2月23日付けの日経MJ(流通新聞)に、ニトリの記事が掲載されています。記事によれば、「2009年2月期に22期連続の増収増益を見込む」という優良企業です。
この会社の経営の特徴について、記事は「商品数の7割を独自で企画し、景気に応じて値段を自在にコントロールできる経営は不況期ほど力を発揮する」と解説しています。
また、ニトリ自身は自社を「SPA(製造小売り)でなく製造物流小売業」と定義しています。これは、「商品の企画、製造、販売はもちろん、物流や検査まですべての業務を自前で賄う超SPAを意味している」のだそうです。
「値段を自在にコントロールできる」のは、すべての業務を自社で行なうことで、自助努力によるコスト管理ができるからです。また、どこで利益を稼ぐか(稼がないのか)、柔軟に決めることもできるでしょう。
ならば、どの企業もこの仕組みをにすればよいはずですが、そういう訳にもいきません。このやり方では、固定費が膨れ上がり、とても耐えられないからです。
多くのアウトソーシングビジネスが成り立つのは、自社でやるよりも、外注した方が安上がりで品質も確保できると、考える企業が多いからです。
そのため、業務の特定部分に「選択と集中」をし、「持たざる経営」で成功している企業が注目されることもあります。二トリと比較すれば、全くの両極端となりますが、どちらも成功できるというのが興味深いです。
記事によると、二トリの「憲法」は、(1)安さ (2)安さ (3)安さ であり、(4)が「適正な品質」となります。固定費を使いながらも、コスト削減の努力は半端でなく、「燃費」の向上への追求には、すさまじいものがあります。
経営者の重要な仕事は、資源の配分を決めることですが、配分さえすれば、自然と結果が出てくるというわけではありません。エンジンを大きくしたら、運転時には、燃費をコントロールした上で、最大限の出力を生むようなマネジメントが必要です。
その方向性が「憲法」で示され、ニトリの社長は、そのための徹底的な議論を尽くします。そうでなくては、この仕組みは成り立ちにくいでしょう。その分、他社はなかなかマネができません。
記事は「国内では今のところ死角はない。不況は長引きそうで、逆風は二トリの成長をさらに押し上げそうだ」としています。マネできないのも当然で、固定費をカットするという、通常の不況対策とは逆を行っているからなのです。
【今日の教訓】
あなたの企業では、不況対策として固定費の削減を考えているのではないだろうか。しかしその前に、固定費の「燃費」を改善し、最大限の出力を得るための最大限の努力をしただろうか。固定費というエンジンを、いかにうまく運転するかが、経営の技術だ。
<参考:日経MJ(流通新聞) 2009.02.23【1面】>
そのようなことは、今まで何度も行なわれてきました。具体的には、人員削減や工場の閉鎖といった取り組みです。やむを得ないことではありますが、それによるダメージもまた、取り沙汰されます。
固定費は、決して「必要悪」なのではありません。収益を稼ぐエンジンのようなものです。エンジンを小さくしてしまえば、当然、収益力などの「出力」が衰えます。それがダメージとなります。
とは言え、エンジンの「燃費」が悪ければ、やはりこのエンジンではマズいということになります。その判断が難しいところですが、それが経営というものでしょう。
2月23日付けの日経MJ(流通新聞)に、ニトリの記事が掲載されています。記事によれば、「2009年2月期に22期連続の増収増益を見込む」という優良企業です。
この会社の経営の特徴について、記事は「商品数の7割を独自で企画し、景気に応じて値段を自在にコントロールできる経営は不況期ほど力を発揮する」と解説しています。
また、ニトリ自身は自社を「SPA(製造小売り)でなく製造物流小売業」と定義しています。これは、「商品の企画、製造、販売はもちろん、物流や検査まですべての業務を自前で賄う超SPAを意味している」のだそうです。
「値段を自在にコントロールできる」のは、すべての業務を自社で行なうことで、自助努力によるコスト管理ができるからです。また、どこで利益を稼ぐか(稼がないのか)、柔軟に決めることもできるでしょう。
ならば、どの企業もこの仕組みをにすればよいはずですが、そういう訳にもいきません。このやり方では、固定費が膨れ上がり、とても耐えられないからです。
多くのアウトソーシングビジネスが成り立つのは、自社でやるよりも、外注した方が安上がりで品質も確保できると、考える企業が多いからです。
そのため、業務の特定部分に「選択と集中」をし、「持たざる経営」で成功している企業が注目されることもあります。二トリと比較すれば、全くの両極端となりますが、どちらも成功できるというのが興味深いです。
記事によると、二トリの「憲法」は、(1)安さ (2)安さ (3)安さ であり、(4)が「適正な品質」となります。固定費を使いながらも、コスト削減の努力は半端でなく、「燃費」の向上への追求には、すさまじいものがあります。
経営者の重要な仕事は、資源の配分を決めることですが、配分さえすれば、自然と結果が出てくるというわけではありません。エンジンを大きくしたら、運転時には、燃費をコントロールした上で、最大限の出力を生むようなマネジメントが必要です。
その方向性が「憲法」で示され、ニトリの社長は、そのための徹底的な議論を尽くします。そうでなくては、この仕組みは成り立ちにくいでしょう。その分、他社はなかなかマネができません。
記事は「国内では今のところ死角はない。不況は長引きそうで、逆風は二トリの成長をさらに押し上げそうだ」としています。マネできないのも当然で、固定費をカットするという、通常の不況対策とは逆を行っているからなのです。
【今日の教訓】
あなたの企業では、不況対策として固定費の削減を考えているのではないだろうか。しかしその前に、固定費の「燃費」を改善し、最大限の出力を得るための最大限の努力をしただろうか。固定費というエンジンを、いかにうまく運転するかが、経営の技術だ。
<参考:日経MJ(流通新聞) 2009.02.23【1面】>
タグ :ニトリ
2009年02月12日
仕事では、一人で何役やってますか?
中小企業では、一人の社員が何役もの仕事をこなさなくてはならないことがよくあります。業務の絶対量が少ないので、それぞれの仕事に専任担当者を割り当てるわけにはいかないからです。
多様な仕事に取り組めることは、中小企業で働く利点だとも言えるでしょう。あれもこれもと仕事をやらされることで、不満を漏らす社員もいるようですが、そのような人は、中小企業には向かないと思います。
2月12日付けの日経産業新聞に、「神奈川県箱根町で8つの温泉旅館・ホテルを運営する一の湯」に関する記事が掲載されています。1630年創業の老舗企業ですが、「低価格の温泉旅館・リゾートホテル」を目指してチェーン展開に積極的です。
この「一の湯」は、「製造業に比べて生産性が劣っているとされるサービス業でありながら、この20年で労働生産性(従業員一人あたりの粗利益)を4倍弱に引き上げた」そうです。
その要因は、「業界の慣習にとらわれずに、サービスの提供の仕方や働き方に独自の工夫」をしていることにあります。たとえば「一人最低でも三役をこなす」のだそうです。
具体的には、受付係が「食事の時間帯には調理や配膳を担当する」といったことまで行ないます。業界の慣習に反するやり方で、「反発してやめる人は少なくなかった」そうだが、残業代を一分単位ですべて支払うなどの施策で、理解を得ることに成功しました。
製造業なら、一人で複数の工程をこなせるようにする「多能工化」への取り組みは一般的です。一人の受け持ち範囲を拡大するのは、「セル生産方式」にも通じるやり方です。
フロントと調理室を同じフロアにしたり、裏口から行き来できるように隣り合わせに配置するなど、「旅館内部のレイアウトにもこだわる」。これも、製造業の工場レイアウトの工夫に通じます。
「箱根に集中展開していることも生産性向上に貢献している」そうです。互いに従業員を行き来させられるからです。これは、小売業のドミナント戦略に相当しますね。
お茶やビールはセルフサービスです。「客室の冷蔵庫を空にして廊下に自動販売機を設置する方式」にもしており、これはビジネスホテルでみられるやり方です。
これらの施策は、意識して「人時生産性」を向上させようとして編み出されたものなのだそうです。あるセミナーで、他社と比較した自社の生産性の低さに、小川晴也社長がショックを受けたことから、取り組みが始まりました。
上述した施策からわかりますが、いずれも他の業界のやり方を自社に上手に採り入れています。他業界から学ぶのですから、業界の慣習にとらわれることもありません。
「製造業に比べて生産性が劣っているとされる」状況にあり、それを「当たり前」と考えず、ならば製造業のやり方をマネしてやろうと言わんばかりの取り組みをしているわけです。
生産性を劇的に向上させるなど、今さら新たなアイデアなど、出しにくいと思うかも知れません。しかしヒントは、他業界からみつけることができます。業界が違うからと、見向きもしないようではいけませんね。
【今日の教訓】
あなたの企業では、自社の生産性を劇的に向上させるために、どのような施策を打つことを考えているだろうか。アイデアは出尽くしたと思うなら、他業界に目を向けてみることだ。業界の慣習にとらわれなければ、実行できるアイデアがいくつもみつかるはずだ。
<参考:日経産業新聞 2009.02.12【18面】>
多様な仕事に取り組めることは、中小企業で働く利点だとも言えるでしょう。あれもこれもと仕事をやらされることで、不満を漏らす社員もいるようですが、そのような人は、中小企業には向かないと思います。
2月12日付けの日経産業新聞に、「神奈川県箱根町で8つの温泉旅館・ホテルを運営する一の湯」に関する記事が掲載されています。1630年創業の老舗企業ですが、「低価格の温泉旅館・リゾートホテル」を目指してチェーン展開に積極的です。
この「一の湯」は、「製造業に比べて生産性が劣っているとされるサービス業でありながら、この20年で労働生産性(従業員一人あたりの粗利益)を4倍弱に引き上げた」そうです。
その要因は、「業界の慣習にとらわれずに、サービスの提供の仕方や働き方に独自の工夫」をしていることにあります。たとえば「一人最低でも三役をこなす」のだそうです。
具体的には、受付係が「食事の時間帯には調理や配膳を担当する」といったことまで行ないます。業界の慣習に反するやり方で、「反発してやめる人は少なくなかった」そうだが、残業代を一分単位ですべて支払うなどの施策で、理解を得ることに成功しました。
製造業なら、一人で複数の工程をこなせるようにする「多能工化」への取り組みは一般的です。一人の受け持ち範囲を拡大するのは、「セル生産方式」にも通じるやり方です。
フロントと調理室を同じフロアにしたり、裏口から行き来できるように隣り合わせに配置するなど、「旅館内部のレイアウトにもこだわる」。これも、製造業の工場レイアウトの工夫に通じます。
「箱根に集中展開していることも生産性向上に貢献している」そうです。互いに従業員を行き来させられるからです。これは、小売業のドミナント戦略に相当しますね。
お茶やビールはセルフサービスです。「客室の冷蔵庫を空にして廊下に自動販売機を設置する方式」にもしており、これはビジネスホテルでみられるやり方です。
これらの施策は、意識して「人時生産性」を向上させようとして編み出されたものなのだそうです。あるセミナーで、他社と比較した自社の生産性の低さに、小川晴也社長がショックを受けたことから、取り組みが始まりました。
上述した施策からわかりますが、いずれも他の業界のやり方を自社に上手に採り入れています。他業界から学ぶのですから、業界の慣習にとらわれることもありません。
「製造業に比べて生産性が劣っているとされる」状況にあり、それを「当たり前」と考えず、ならば製造業のやり方をマネしてやろうと言わんばかりの取り組みをしているわけです。
生産性を劇的に向上させるなど、今さら新たなアイデアなど、出しにくいと思うかも知れません。しかしヒントは、他業界からみつけることができます。業界が違うからと、見向きもしないようではいけませんね。
【今日の教訓】
あなたの企業では、自社の生産性を劇的に向上させるために、どのような施策を打つことを考えているだろうか。アイデアは出尽くしたと思うなら、他業界に目を向けてみることだ。業界の慣習にとらわれなければ、実行できるアイデアがいくつもみつかるはずだ。
<参考:日経産業新聞 2009.02.12【18面】>
2009年02月10日
勝つための条件を積み上げていくとは?
よかれと思って取り組んだにも関わらず、結果は逆効果となってしまうことがあり得ます。たとえば、口コミ。自社の商品が評判となり、売れ行きが加速することを期待します。
しかし、悪評が広まってしまう可能性もあります。「両刃の剣」となるわけです。コントロールされていないことが口コミの価値ですから、致し方ないことかも知れません。
収益拡大のために新商品の投入を図っても、その品質に問題があれば、裏目に出てしまいます。その商品だけの問題ならまだしも、それがブランド価値を損ねてしまう危険性もあります。
企業側の思惑がいかようにあろうとも、顧客に価値を感じてもらえなければ、極端な話、見向きもされなかったりします。顧客を「囲い込む」などというのは、実におこがましい話で、顧客は決して囲い込まれたいとは思っていませんよね。
2月10日付けの日経産業新聞に、「ネット求人大手のエン・ジャパンは企業内教育を手掛けるレビックグローバルと提携し、eラーニングによる企業の採用内定者向け研修を始める」という記事が掲載されています。
記事によれば、「レビックグローバルの内定者向けeラーニングは大手企業向けにはすでに導入実績が」あるとのことです。一方、eラーニングの「中堅・中小企業での導入はまだ少な」いそうです。
エン・ジャパンの主要顧客層は中堅・中小企業ですから、それらの企業向けに、eラーニングを売ろうというわけです。まだ導入が少ないので、「販売余地が大きい」と判断してのことです。
エン・ジャパンの立場からすると、内定者向けeラーニングは、自社の顧客層に対する新商品となり、収益拡大策として有効とみられます。特に求人が冷え込んでいる環境下にあって、新商品の投入は重要でしょう。
同社は既に、「内定者や新入社員向けの対面式の研修」を手掛けていますが、それとの「相乗効果創出」を狙い、「eラーニングと対面式研修とのセット販売も進める予定」だそうです。
単純に他社サービスを既存顧客に流すだけではなく、自社ならではの付加価値をつけようという取り組みに、注目すべきでしょう。その意図として、「充実した研修事業を売り込むことにより、就職サイトの顧客網の囲い込みや拡大にもつなげたい考え」があります。
先述のように、新商品を投入しても、その評価がイマイチであれば、顧客を囲い込むどころか、愛想を尽かされてしまうリスクがありあます。提携他社に依存した、安易な新商品投入で済ませるわけにはいかないのです。
そもそも、販売する企業にとっては「新商品」であっても、既に世の中で流通しているとすれば、「新商品」でも何でもありません。「新商品」=売上の拡大というのは、実に甘い考えだと言えます。
その意味でも、新商品投入・新規事業参入には、慎重な戦略をとることが求められます。「新参者」が勝つには、それなりの備えが必要なのは、当然のことでしょう。
エン・ジャパンの場合、セット販売による「充実した研修事業」という、競争力が高いであろう商品をつくり、なおかつ、まだ導入が少ない中堅・中小企業という、比較的競争が穏やかな市場を狙うことで、勝つための条件を押さえる姿勢がみられます。
勝つべくして勝つのが、兵法の極意だといわれます。決して安易な参入はしないのです。勝つための条件を積み上げ、万全にして取り組む姿勢は
どの企業にも求められるでしょう。
【今日の教訓】
あなたは、新商品投入・新規事業立ち上げにあたり、「勝つべくして勝つ」条件を、どれだけ積み上げることをしているだろうか。安易な取り組みで失敗するケースは、後を絶たない。十分な条件整備をし、思惑ハズレで後悔することがないようにしよう。
<参考:日経産業新聞 2009.02.10【16面】>
しかし、悪評が広まってしまう可能性もあります。「両刃の剣」となるわけです。コントロールされていないことが口コミの価値ですから、致し方ないことかも知れません。
収益拡大のために新商品の投入を図っても、その品質に問題があれば、裏目に出てしまいます。その商品だけの問題ならまだしも、それがブランド価値を損ねてしまう危険性もあります。
企業側の思惑がいかようにあろうとも、顧客に価値を感じてもらえなければ、極端な話、見向きもされなかったりします。顧客を「囲い込む」などというのは、実におこがましい話で、顧客は決して囲い込まれたいとは思っていませんよね。
2月10日付けの日経産業新聞に、「ネット求人大手のエン・ジャパンは企業内教育を手掛けるレビックグローバルと提携し、eラーニングによる企業の採用内定者向け研修を始める」という記事が掲載されています。
記事によれば、「レビックグローバルの内定者向けeラーニングは大手企業向けにはすでに導入実績が」あるとのことです。一方、eラーニングの「中堅・中小企業での導入はまだ少な」いそうです。
エン・ジャパンの主要顧客層は中堅・中小企業ですから、それらの企業向けに、eラーニングを売ろうというわけです。まだ導入が少ないので、「販売余地が大きい」と判断してのことです。
エン・ジャパンの立場からすると、内定者向けeラーニングは、自社の顧客層に対する新商品となり、収益拡大策として有効とみられます。特に求人が冷え込んでいる環境下にあって、新商品の投入は重要でしょう。
同社は既に、「内定者や新入社員向けの対面式の研修」を手掛けていますが、それとの「相乗効果創出」を狙い、「eラーニングと対面式研修とのセット販売も進める予定」だそうです。
単純に他社サービスを既存顧客に流すだけではなく、自社ならではの付加価値をつけようという取り組みに、注目すべきでしょう。その意図として、「充実した研修事業を売り込むことにより、就職サイトの顧客網の囲い込みや拡大にもつなげたい考え」があります。
先述のように、新商品を投入しても、その評価がイマイチであれば、顧客を囲い込むどころか、愛想を尽かされてしまうリスクがありあます。提携他社に依存した、安易な新商品投入で済ませるわけにはいかないのです。
そもそも、販売する企業にとっては「新商品」であっても、既に世の中で流通しているとすれば、「新商品」でも何でもありません。「新商品」=売上の拡大というのは、実に甘い考えだと言えます。
その意味でも、新商品投入・新規事業参入には、慎重な戦略をとることが求められます。「新参者」が勝つには、それなりの備えが必要なのは、当然のことでしょう。
エン・ジャパンの場合、セット販売による「充実した研修事業」という、競争力が高いであろう商品をつくり、なおかつ、まだ導入が少ない中堅・中小企業という、比較的競争が穏やかな市場を狙うことで、勝つための条件を押さえる姿勢がみられます。
勝つべくして勝つのが、兵法の極意だといわれます。決して安易な参入はしないのです。勝つための条件を積み上げ、万全にして取り組む姿勢は
どの企業にも求められるでしょう。
【今日の教訓】
あなたは、新商品投入・新規事業立ち上げにあたり、「勝つべくして勝つ」条件を、どれだけ積み上げることをしているだろうか。安易な取り組みで失敗するケースは、後を絶たない。十分な条件整備をし、思惑ハズレで後悔することがないようにしよう。
<参考:日経産業新聞 2009.02.10【16面】>
2009年02月09日
値下げは値札の書き換えではない。
ビジネスプランを考える際は、このビジネスでの競争に勝つためのカギとなるポイントは何か、押さえる必要があります。そのことをKFS(Key Factor for Success)と呼んだりもします。
頭の中で想像することも可能といえば可能ですが、できれば、データにより検証したいところです。その際に役立つのが、同業の複数社を比較してみることです。
業種によって不況・好況が明確に分かれるケースも多いですが、同じ業界の中でも、業績の良い企業と悪い企業がはっきりと区別されることもあり、極端な場合は、業績が「二極化」します。
対極にあるそれぞれの企業(群)について、ビジネスモデルや戦略・戦術の特徴がわかれば、それが成否のカギだということがわかります。競争の「ルール」が判明するわけです。
2月9日付けの日経MJ(流通新聞)に、「食品スーパーでの収益力の二極化が鮮明になってきた」という記事が掲載されています。記事の見出しに「二極化」という言葉があれば、その違いは何なのかを必ずチェックし、「ルール」を確認してみるとよいでしょう。
食品スーパーの場合、記事によれば、「セールや値下げを強化した」企業が「好調を維持している」そうです。その反対に、「対応が遅れ」、大手の「値下げ攻勢で苦戦を強いられる」ケースが起きているといいます。
結局のところ価格競争か、という話では面白くないのですが、現実は現実として、受け入れる必要があるでしょう。安易なことでは困りますが、適切かつ機敏な値下げ対応は、業績を確保する武器であることは間違いありません。
記事で「好調」として取り上げられているのが、まずマルエツ。「既存店売上高は昨年12月まで26カ月連続で前年同月を上回り、1月も増収を維持しもようだ」とのこと。「好調持続の最大のカギは徹底した低価格戦略」だと記事は解説しています。
また、「オオゼキは直接仕入れなどを拡大し、青果の値引き販売を実施」したことで、「集客に大きな効果がでている」そうです。「ヤオコーの2008年4~12月期連結決算は営業利益が12%伸びた」といいます。特売セールの頻繁な実施と「商品の量を減らしてでも単価を下げる手
法を併用している」そうです。
「一方、売り上げが伸び悩むスーパーも増えている」として、まずエコスが取り上げられています。「品ぞろえを大手総合スーパー並みに広げた結果、加工食品などの仕入れ効率が悪化し、十分に値下げができなかった」とのこと。
そのほか、好調事例として、「均一セールが奏功」したとしてライフコーポレーションが、不振事例として「価格志向への対応が弱かった」とするいなげやが取り上げられています。
いずれにしろ、現象としては「セールと値下げ」が出来たか出来なかったの違いですが、戦略的見地では、「選択と集中」の徹底・不徹底が勝敗を分けています。
特にエコスの場合はわかりやすいです。品ぞろえの拡散が、価格競争力の低下を招いてしまったわけです。「値下げ」とは、値札を書き換える作業のことではないのです。それが出来る仕組みの裏付けがあって、初めて実現し得る技術だと認識する必要がありますす。
「結局のところ価格競争か、という話では面白くない」と先述しましたが、実のところ、その裏側を読み解くことが大切です。日頃の戦略的な取り組みが、いざという時にものを言うのです。
【今日の教訓】
あなたは、自社が属する業界で成功を収めるためのカギは何か、明確に意識しているだろうか。そのカギを押さえるために、どのような仕掛けが必要かを意識した上で、戦略を立てているだろうか。それが出来ていないと、環境変化の波に翻弄されることとなる。
<参考:日経MJ(流通新聞) 2009.02.08【7面】>
頭の中で想像することも可能といえば可能ですが、できれば、データにより検証したいところです。その際に役立つのが、同業の複数社を比較してみることです。
業種によって不況・好況が明確に分かれるケースも多いですが、同じ業界の中でも、業績の良い企業と悪い企業がはっきりと区別されることもあり、極端な場合は、業績が「二極化」します。
対極にあるそれぞれの企業(群)について、ビジネスモデルや戦略・戦術の特徴がわかれば、それが成否のカギだということがわかります。競争の「ルール」が判明するわけです。
2月9日付けの日経MJ(流通新聞)に、「食品スーパーでの収益力の二極化が鮮明になってきた」という記事が掲載されています。記事の見出しに「二極化」という言葉があれば、その違いは何なのかを必ずチェックし、「ルール」を確認してみるとよいでしょう。
食品スーパーの場合、記事によれば、「セールや値下げを強化した」企業が「好調を維持している」そうです。その反対に、「対応が遅れ」、大手の「値下げ攻勢で苦戦を強いられる」ケースが起きているといいます。
結局のところ価格競争か、という話では面白くないのですが、現実は現実として、受け入れる必要があるでしょう。安易なことでは困りますが、適切かつ機敏な値下げ対応は、業績を確保する武器であることは間違いありません。
記事で「好調」として取り上げられているのが、まずマルエツ。「既存店売上高は昨年12月まで26カ月連続で前年同月を上回り、1月も増収を維持しもようだ」とのこと。「好調持続の最大のカギは徹底した低価格戦略」だと記事は解説しています。
また、「オオゼキは直接仕入れなどを拡大し、青果の値引き販売を実施」したことで、「集客に大きな効果がでている」そうです。「ヤオコーの2008年4~12月期連結決算は営業利益が12%伸びた」といいます。特売セールの頻繁な実施と「商品の量を減らしてでも単価を下げる手
法を併用している」そうです。
「一方、売り上げが伸び悩むスーパーも増えている」として、まずエコスが取り上げられています。「品ぞろえを大手総合スーパー並みに広げた結果、加工食品などの仕入れ効率が悪化し、十分に値下げができなかった」とのこと。
そのほか、好調事例として、「均一セールが奏功」したとしてライフコーポレーションが、不振事例として「価格志向への対応が弱かった」とするいなげやが取り上げられています。
いずれにしろ、現象としては「セールと値下げ」が出来たか出来なかったの違いですが、戦略的見地では、「選択と集中」の徹底・不徹底が勝敗を分けています。
特にエコスの場合はわかりやすいです。品ぞろえの拡散が、価格競争力の低下を招いてしまったわけです。「値下げ」とは、値札を書き換える作業のことではないのです。それが出来る仕組みの裏付けがあって、初めて実現し得る技術だと認識する必要がありますす。
「結局のところ価格競争か、という話では面白くない」と先述しましたが、実のところ、その裏側を読み解くことが大切です。日頃の戦略的な取り組みが、いざという時にものを言うのです。
【今日の教訓】
あなたは、自社が属する業界で成功を収めるためのカギは何か、明確に意識しているだろうか。そのカギを押さえるために、どのような仕掛けが必要かを意識した上で、戦略を立てているだろうか。それが出来ていないと、環境変化の波に翻弄されることとなる。
<参考:日経MJ(流通新聞) 2009.02.08【7面】>
2009年02月04日
店内在庫の削減が、なぜ調剤事業強化につながるのか?
経営にはバランスが必要だと言えば、そのとおりだと思う人は多いでしょう。しかし、戦略に関して言えば、「選択と集中」という言葉が示すように、あえてバランスを崩すことが必要となります
よく言われるのが、「強み」に集中せよということです。総花的な施策は、結局のところ、たいした成果を生むことはできません。劇的な成果は、劇的なアンバランスから生まれます。
何に集中すべきかが明確に意識されていれば、次の打ち手をどうするかは、自明の理となります。その前提は、戦略が明確になっているか、すなわち、どう戦うべきかがわかっているということでしょう。
2月4日付けの日経MJ(流通新聞)に、ドラッグストアの「セガミメディクスが調剤事業の強化に向けて、店内在庫の削減に努めている」という記事が掲載されています。
在庫を削減して、資金効率を高めるのは、どの企業も目指すところでしょう。セガミの場合、「自動発注システムに頼っていた注文方法の見直し」を行なうことで、それを実現します。
記事によれば、自動発注システムにも限界があるため、「立地環境に精通した店長」が、天候や近隣のイベントなどを勘案し、発注を決めるようにしたのだそうです。
それはよいとして、では、店内在庫の削減が、どうして調剤事業の強化につながるのでしょうか。発注の精度を高めることが、セガミの「強み」とどう結びつくのでしょうか。記事を読み進めていくと、そのロジックがわかります。
在庫を削減することで、「約500平米の店舗の場合、一割程度とされる倉庫面積を縮小させることができるようになる」そうです。その「空いた空間を調剤室の一部として活用すること」ができるようになります。
記事によれば、セガミはもともと「調剤事業に強み」があります。「現在の同事業の年間売上高は160億円で業界首位だ」そうです。それでも、現時点での調剤併設率は17%にとどまります。つまり、「強み」を伸ばす余地は、まだまだあるということなのです。
「強み」をどうやって伸ばすかを考えるには、何が制約要因になっているかを分析してみるのが有効です。セガミの場合、それは店舗スペースであり、余剰な在庫を抱えていることが問題として認識されたわけです。
発注精度を高め、欠品を防止し、適切な品揃えを実現できれば、それだけでも「強み」となり得ます。しかし、真の狙いは、その先にある、調剤事業の強化にあります。
「強み」のさらなる強化はアンバランスをもたらしますが、とは言え、人間の体のように、各業務は相互に連携していますので、特化した部分への集中は、他の部分の変革を要求します。その意味で、経営のバランスを考えることが大切なのです。
一方で調剤事業を強化し、他方で発注精度を高めておこうというのは、総花的な発想に近いでしょう。そうではなく、調剤事業のさらなる強化のために、発注精度向上にも取り組む。それが「選択と集中」であり、真の意味での経営のバランスだと言えます。
「強み」を強化することを徹底的に考えると、それは部分的な強化にとどまらず、あらゆる面に変革が要求されます。それは決して、総花的ということではありません。
【今日の教訓】
あなたの企業では、一つの明確な戦略方針に基づいた「選択と集中」がなされているだろうか。それは必ずしも社内の特定部分に特化することではない。むしろ、全社の各部分が、戦略方針に則って変革せざるを得ないという影響が及ぶと考えた方がよい。
<参考:日経MJ(流通新聞) 2009.02.04【5面】>
よく言われるのが、「強み」に集中せよということです。総花的な施策は、結局のところ、たいした成果を生むことはできません。劇的な成果は、劇的なアンバランスから生まれます。
何に集中すべきかが明確に意識されていれば、次の打ち手をどうするかは、自明の理となります。その前提は、戦略が明確になっているか、すなわち、どう戦うべきかがわかっているということでしょう。
2月4日付けの日経MJ(流通新聞)に、ドラッグストアの「セガミメディクスが調剤事業の強化に向けて、店内在庫の削減に努めている」という記事が掲載されています。
在庫を削減して、資金効率を高めるのは、どの企業も目指すところでしょう。セガミの場合、「自動発注システムに頼っていた注文方法の見直し」を行なうことで、それを実現します。
記事によれば、自動発注システムにも限界があるため、「立地環境に精通した店長」が、天候や近隣のイベントなどを勘案し、発注を決めるようにしたのだそうです。
それはよいとして、では、店内在庫の削減が、どうして調剤事業の強化につながるのでしょうか。発注の精度を高めることが、セガミの「強み」とどう結びつくのでしょうか。記事を読み進めていくと、そのロジックがわかります。
在庫を削減することで、「約500平米の店舗の場合、一割程度とされる倉庫面積を縮小させることができるようになる」そうです。その「空いた空間を調剤室の一部として活用すること」ができるようになります。
記事によれば、セガミはもともと「調剤事業に強み」があります。「現在の同事業の年間売上高は160億円で業界首位だ」そうです。それでも、現時点での調剤併設率は17%にとどまります。つまり、「強み」を伸ばす余地は、まだまだあるということなのです。
「強み」をどうやって伸ばすかを考えるには、何が制約要因になっているかを分析してみるのが有効です。セガミの場合、それは店舗スペースであり、余剰な在庫を抱えていることが問題として認識されたわけです。
発注精度を高め、欠品を防止し、適切な品揃えを実現できれば、それだけでも「強み」となり得ます。しかし、真の狙いは、その先にある、調剤事業の強化にあります。
「強み」のさらなる強化はアンバランスをもたらしますが、とは言え、人間の体のように、各業務は相互に連携していますので、特化した部分への集中は、他の部分の変革を要求します。その意味で、経営のバランスを考えることが大切なのです。
一方で調剤事業を強化し、他方で発注精度を高めておこうというのは、総花的な発想に近いでしょう。そうではなく、調剤事業のさらなる強化のために、発注精度向上にも取り組む。それが「選択と集中」であり、真の意味での経営のバランスだと言えます。
「強み」を強化することを徹底的に考えると、それは部分的な強化にとどまらず、あらゆる面に変革が要求されます。それは決して、総花的ということではありません。
【今日の教訓】
あなたの企業では、一つの明確な戦略方針に基づいた「選択と集中」がなされているだろうか。それは必ずしも社内の特定部分に特化することではない。むしろ、全社の各部分が、戦略方針に則って変革せざるを得ないという影響が及ぶと考えた方がよい。
<参考:日経MJ(流通新聞) 2009.02.04【5面】>
2009年01月29日
音楽ソフトの通販ルート売上比率が上昇中です
事業を定義する際は、3つの要素で考えます。すなわち、「顧客」「商品」「販売システム」の3つです。どれか1つでも異なれば、違う事業単位となります。新規事業のアイデアを生むためには、どれか1つを変えてみればどうか、と考えてみます。
「顧客」と「商品」の組み合わせが同じであり、市場規模も縮小していないのに、売上が急減したとします。その場合、「販売システム」に原因があると考えることができます。
「販売システム」は、販売チャネルと考えてもよいでしょう。顧客視点で言えば、同じ商品でも、今までとは別の店で買うようになれば、「販売システム」が変わったことになります。
どのような「顧客」「商品」「販売システム」の組み合わせを狙うかが、まさに戦略です。上述のように、そのうちの「販売システム」の選択を間違えると、同じ「顧客」「商品」でも、成果を上げられないことになります。
1月29日付けの日経産業新聞に、「ユニバーサルミュージックは会員組織を新設し、音楽ソフトの通信販売事業を本格展開する」という記事が掲載されています。
CDやDVD、BD(ブルーレイ・ディスク)のような音楽ソフトは、かつては「レコード屋」で買うものでした。しかし今や、「販売システム」が変わってきています。
そのことについて、記事は、「小売店での音楽ソフト販売が減速傾向にある中で、通販など特定ルート向けに企画・販売する特販商品は、レコード会社の売上高に占める比重が高まりつつある」と指摘しています。
小売店で1枚ずつ売るのではなく、会員組織を立ち上げ、通信販売という売り方で売る。その新しい売り方(販売システム)での販売を伸ばそうというわけです。
事業単位が異なれば、事業のコンセプトも違ってくるので、組織は分けた方がよいです。記事によれば、「ビクターエンタテインメントと星光堂は特販商品に特化した共同出資会社を2月に設立する」とのことです。セオリー通りの取り組みです。
ユニバーサルミュージックが立ち上げる会員組織では、「クラシック音楽と、海外の音楽とゆかりの深い美しい風景をハイビジョン映像で収録した」という「音楽・夢紀行」なる商品を、「全24巻セットから1巻ずつ毎月届ける」のだそうです。いわゆる頒布会方式の売り方です。
ターゲット顧客は「普段は音楽ソフトの購入金額が少ない50~60代」の人たちとなります。事業の3要素のうち、「販売システム」を変えることで、「顧客」の潜在需要を顕在化させることができるわけです。
「商品」についても、従来の音楽ソフトとは異なり、セットものとなります。事業の3要素のうち、「販売システム」の変更に伴い、「商品」も変更になっています。
「顧客」「商品」「販売システム」は、それぞれ独立した別個の存在ではなく、相互に依存しています。考えてみれば当然のことでしょう。女性向けの商品を買うのは、主に女性であり、女性が好むお店も、ある程度は特定されるからです。
業績を拡大する戦略を策定するにあたっては、冒頭で述べたとおり、「顧客」「商品」「販売システム」のうち、まずはいずれかの要素を変えることを考えてみると、ヒントを得られます。
しかし実際に成果を上げるには、単純に1つを変えるだけでは不十分で、1つを変えることに伴い、残りの2つもアレンジしていくことが必要となります。結果として、3つの要素がそれぞれ、上手い具合に最適化されることになるわけです。
【今日の教訓】
「顧客」「商品」「販売システム」のうち、まずはどれか1つを変えることで、新たな事業を立ち上げられないか、考えてみよう。それを具体化するにあたっては、その1つだけではなく、他の2つの要素についても変更を加え、最適化しよう。
<参考:日経産業新聞 2009.01.29【4面】>
「顧客」と「商品」の組み合わせが同じであり、市場規模も縮小していないのに、売上が急減したとします。その場合、「販売システム」に原因があると考えることができます。
「販売システム」は、販売チャネルと考えてもよいでしょう。顧客視点で言えば、同じ商品でも、今までとは別の店で買うようになれば、「販売システム」が変わったことになります。
どのような「顧客」「商品」「販売システム」の組み合わせを狙うかが、まさに戦略です。上述のように、そのうちの「販売システム」の選択を間違えると、同じ「顧客」「商品」でも、成果を上げられないことになります。
1月29日付けの日経産業新聞に、「ユニバーサルミュージックは会員組織を新設し、音楽ソフトの通信販売事業を本格展開する」という記事が掲載されています。
CDやDVD、BD(ブルーレイ・ディスク)のような音楽ソフトは、かつては「レコード屋」で買うものでした。しかし今や、「販売システム」が変わってきています。
そのことについて、記事は、「小売店での音楽ソフト販売が減速傾向にある中で、通販など特定ルート向けに企画・販売する特販商品は、レコード会社の売上高に占める比重が高まりつつある」と指摘しています。
小売店で1枚ずつ売るのではなく、会員組織を立ち上げ、通信販売という売り方で売る。その新しい売り方(販売システム)での販売を伸ばそうというわけです。
事業単位が異なれば、事業のコンセプトも違ってくるので、組織は分けた方がよいです。記事によれば、「ビクターエンタテインメントと星光堂は特販商品に特化した共同出資会社を2月に設立する」とのことです。セオリー通りの取り組みです。
ユニバーサルミュージックが立ち上げる会員組織では、「クラシック音楽と、海外の音楽とゆかりの深い美しい風景をハイビジョン映像で収録した」という「音楽・夢紀行」なる商品を、「全24巻セットから1巻ずつ毎月届ける」のだそうです。いわゆる頒布会方式の売り方です。
ターゲット顧客は「普段は音楽ソフトの購入金額が少ない50~60代」の人たちとなります。事業の3要素のうち、「販売システム」を変えることで、「顧客」の潜在需要を顕在化させることができるわけです。
「商品」についても、従来の音楽ソフトとは異なり、セットものとなります。事業の3要素のうち、「販売システム」の変更に伴い、「商品」も変更になっています。
「顧客」「商品」「販売システム」は、それぞれ独立した別個の存在ではなく、相互に依存しています。考えてみれば当然のことでしょう。女性向けの商品を買うのは、主に女性であり、女性が好むお店も、ある程度は特定されるからです。
業績を拡大する戦略を策定するにあたっては、冒頭で述べたとおり、「顧客」「商品」「販売システム」のうち、まずはいずれかの要素を変えることを考えてみると、ヒントを得られます。
しかし実際に成果を上げるには、単純に1つを変えるだけでは不十分で、1つを変えることに伴い、残りの2つもアレンジしていくことが必要となります。結果として、3つの要素がそれぞれ、上手い具合に最適化されることになるわけです。
【今日の教訓】
「顧客」「商品」「販売システム」のうち、まずはどれか1つを変えることで、新たな事業を立ち上げられないか、考えてみよう。それを具体化するにあたっては、その1つだけではなく、他の2つの要素についても変更を加え、最適化しよう。
<参考:日経産業新聞 2009.01.29【4面】>
2009年01月28日
表に出てこない不満はどうやって察知しますか?
不況がいよいよひどくなり、経済対策の有効性には疑問が呈されています。特効薬となる妙案はないのかも知れませんが、失業などで苦しむ国民の気持ちを、為政者が理解していないのではという不満も多いのだと思います。
歴史をひもとけば、仁徳天皇は、人家のかまどから炊煙が立ち上っていないのに気づき、租税を免除したという話が伝わっています。その間、自らは倹約に努めたそうです。
かまどの煙の有無を見ただけで、民衆の苦労を「察知」する為政者をいただくことは、国民にとって幸福なことだと思います。昨今の政治状況と比較し、溜息をつきたくもなります。
一つの事象を見て、何に気づくことができるか、その感性が求められるのは、政治もビジネスも同じことでしょう。ビジネスであれば、それがチャンスに直結します。
1月28日付けの日経産業新聞に、「段ボール箱にひもなどを自動で結ぶ梱包用装置のトップメーカー」である「ストラパック」という会社についての記事が掲載されています。
同社がトップメーカーとなった契機は、1974年に「油のいらない新製品」を開発したことだそうです。油が装置に付着することで、梱包対象となる段ボールに油が染み込むという問題を解決したのです。
そして、業界トップを維持するために、製品開発に力を入れてきています。顧客からのクレームに対応するのはもちろんのこと、「表に出てきにくい裏の不満」を「察知」する仕組みを持っているところがすごいです。
まず、クレームについては「クレーム書」に書面化し、「見える化」します。これは、わかりやすいですね。そして、「表に出てきにくい裏の不満はスペア部品を基準に探る」のだそうです。
具体的には、「スペア部品の出荷量から一番多いものに注目」し、「頻繁に部品が交換される=耐久性や利便性の問題が隠れている」と判断するわけです。
このような推定は、ストラパック社や仁徳天皇ならずとも、気のきいた人なら、日頃から行なっているでしょう。とは言え、指摘されてはじめて「なるほど」と思わされたりもします。
要は、先述のとおり、一つの事象を見て、そのような推定ができる感性を持ち合わせているかどうかということです。この考え方は、いわゆる「先行指標」で市場動向を予測するのと同じです。
民が貧しいから炊煙が立たない、耐久性に問題があるから部品交換が頻繁に起こる、という具合に、原因と結果の関係を見抜く力は、ビジネスで役立ちます。
ストラパックの取り組みの場合、問題を「発見」する感性・意識についても見習いたいところです。部品交換をすれば、メーカーとしての義務は果たしたことになるでしょう。しかし、それで済ませては進歩がありません。その感性を磨く必要があるのです。
たとえば、「問い合わせ」には回答すれば、事が済みます。ですが、説明が不足していることへの「クレーム」だと解釈すれば、受け止め方も対応も、大きく変わるはずです。「問い合わせ」を手間を惜しみ、去ってしまった見込み客は多いかも知れないのです。
【今日の教訓】
あなたの企業では、隠れて見えない問題を発見する仕組みを持っているだろうか。原因と結果の関係を見抜く感性があれば、そのような問題でも発見することができる。今一度、身の回りで起こっている事象をよく吟味してみよう。
<参考:日経産業新聞 2009.01.28【19面】>
歴史をひもとけば、仁徳天皇は、人家のかまどから炊煙が立ち上っていないのに気づき、租税を免除したという話が伝わっています。その間、自らは倹約に努めたそうです。
かまどの煙の有無を見ただけで、民衆の苦労を「察知」する為政者をいただくことは、国民にとって幸福なことだと思います。昨今の政治状況と比較し、溜息をつきたくもなります。
一つの事象を見て、何に気づくことができるか、その感性が求められるのは、政治もビジネスも同じことでしょう。ビジネスであれば、それがチャンスに直結します。
1月28日付けの日経産業新聞に、「段ボール箱にひもなどを自動で結ぶ梱包用装置のトップメーカー」である「ストラパック」という会社についての記事が掲載されています。
同社がトップメーカーとなった契機は、1974年に「油のいらない新製品」を開発したことだそうです。油が装置に付着することで、梱包対象となる段ボールに油が染み込むという問題を解決したのです。
そして、業界トップを維持するために、製品開発に力を入れてきています。顧客からのクレームに対応するのはもちろんのこと、「表に出てきにくい裏の不満」を「察知」する仕組みを持っているところがすごいです。
まず、クレームについては「クレーム書」に書面化し、「見える化」します。これは、わかりやすいですね。そして、「表に出てきにくい裏の不満はスペア部品を基準に探る」のだそうです。
具体的には、「スペア部品の出荷量から一番多いものに注目」し、「頻繁に部品が交換される=耐久性や利便性の問題が隠れている」と判断するわけです。
このような推定は、ストラパック社や仁徳天皇ならずとも、気のきいた人なら、日頃から行なっているでしょう。とは言え、指摘されてはじめて「なるほど」と思わされたりもします。
要は、先述のとおり、一つの事象を見て、そのような推定ができる感性を持ち合わせているかどうかということです。この考え方は、いわゆる「先行指標」で市場動向を予測するのと同じです。
民が貧しいから炊煙が立たない、耐久性に問題があるから部品交換が頻繁に起こる、という具合に、原因と結果の関係を見抜く力は、ビジネスで役立ちます。
ストラパックの取り組みの場合、問題を「発見」する感性・意識についても見習いたいところです。部品交換をすれば、メーカーとしての義務は果たしたことになるでしょう。しかし、それで済ませては進歩がありません。その感性を磨く必要があるのです。
たとえば、「問い合わせ」には回答すれば、事が済みます。ですが、説明が不足していることへの「クレーム」だと解釈すれば、受け止め方も対応も、大きく変わるはずです。「問い合わせ」を手間を惜しみ、去ってしまった見込み客は多いかも知れないのです。
【今日の教訓】
あなたの企業では、隠れて見えない問題を発見する仕組みを持っているだろうか。原因と結果の関係を見抜く感性があれば、そのような問題でも発見することができる。今一度、身の回りで起こっている事象をよく吟味してみよう。
<参考:日経産業新聞 2009.01.28【19面】>
2009年01月27日
検索エンジン対策依存は終わるか?
若い頃、ガールフレンドと一緒に映画を観るのは、あまり好きではありませんでした。映画を観るという作業そのものは、一人で出来ることです。わざわざ二人でやる必要はないでしょう。
特に、若い二人なら、二人でしかできない、やりたいことがあるはずではないか! と思ったりしたものです(何を想像しましたか?)。とは言え、年齢が高くなるにつれ、二人で映画を観ることの良さもわかってきました。
同じ映画を観て、感動を共有するのは、すばらしいことです。映画の後の食事も、それで話が弾みます。(もっとも、評価が分かれて関係が険悪になってしまった経験もあるのですが・・)
感動を共有することも含め、何か共通点があると、人間同士は親しくなりやすいものです。出身地が同じ、といったことでも、それを知るのと知らないのとでは、親しくなりやすさに、だいぶ違いがあるように思います。
1月27日付けの日経産業新聞に、「ネットベンチャーのクラウドロイド(東京・渋谷、吉田秀史社長)は、新型の交流サービスを開発した」という記事が掲載されています。
「スピーキー」という名前のサービスで、「同じウェブサイトを見ている登録会員を閲覧ソフト(ブラウザー)の端に表示。会員間でチャット形式のやりとりができる」のだそうです。
「動画視聴や物品販売など同一サイトを見ている会員同士、共通の話題が見つけやすく会話が弾むという」。同じサイトを閲覧しているという「共通点」が、見知らぬ同士を引き寄せ合うわけです。
スピーキーは、専用ソフトをダウンロードして使います。ログインすると、アバター(ネット上の分身)が表示されます。チャットができるだけでなく、「利用者同士が連れ立って別のサイトに移動する機能も搭載」しているそうです。
利用は無料ですが、専用画面にバナー広告を表示して収益を上げるモデルです。「会員属性やサイト閲覧履歴などに応じて効率的な広告を表示できる」、いわゆる行動ターゲティング広告の手法が使われます。
他にも同様のサービスがあり、「昨年夏に準備版を開設したウェブリンは、早くも200万人の登録者を獲得」しているそうです。広告モデルはまだ確立しているとは言えず、「異業種と提携して活用方法を模索している」段階だそうですが。
いずれにしろ、何か「共通点」を軸にすることで、交流チャンスが生まれるという原理が働いています。ビジネスの観点で見れば、交流は口コミのチャンスでもあります。
スピーキーの場合、「会員の閲覧履歴が蓄積される」ので、「このサイトを見ている人はこんなサイトも見ています」といった推薦機能も備わります。好みが共通している相手を介し、今まで知らなかったサイトをみつけることもできるわけです。
サイト運営者にしてみれば、自サイトが閲覧される可能性が広がります。とは言え逆に、自サイトからライバルサイトに閲覧者が流れる可能性も増大します。検索エンジン経由でサイトがアクセスされるのを「縦糸」だとすれば、スピーキーのようなサービスを経由する場合は「横糸」だと言えるでしょう。
従来の「横糸」は、リンクを貼るかどうか、サイト運営者の裁量に任されていましたが、そうも行かなくなってきます。利用者にとっては便利なことですが、サイト間の比較・競争は、縦糸・横糸の両面で行なわれるようになります。
それはすなわち、優勝劣敗が、よりはっきりするようになるということです。淘汰の波が押し寄せ、「本物」だけが生き残ります。サイトの選別が、「縦糸」である検索エンジン任せでなくなれば、ネット上での競争のルールも、現在とは変わらざるを得なくなるでしょうね。
【今日の教訓】
あなたの企業では、サイト閲覧者の行動をどこまで把握しているだろうか。スピーキーやウェブリンのようなサービスが普及すれば、他の誰を連れてきてくれるかまで把握することが必要となる。淘汰の波を勝ち残る策を、今のうちから考えておこう。
<参考:日経産業新聞 2009.01.27【3面】>
特に、若い二人なら、二人でしかできない、やりたいことがあるはずではないか! と思ったりしたものです(何を想像しましたか?)。とは言え、年齢が高くなるにつれ、二人で映画を観ることの良さもわかってきました。
同じ映画を観て、感動を共有するのは、すばらしいことです。映画の後の食事も、それで話が弾みます。(もっとも、評価が分かれて関係が険悪になってしまった経験もあるのですが・・)
感動を共有することも含め、何か共通点があると、人間同士は親しくなりやすいものです。出身地が同じ、といったことでも、それを知るのと知らないのとでは、親しくなりやすさに、だいぶ違いがあるように思います。
1月27日付けの日経産業新聞に、「ネットベンチャーのクラウドロイド(東京・渋谷、吉田秀史社長)は、新型の交流サービスを開発した」という記事が掲載されています。
「スピーキー」という名前のサービスで、「同じウェブサイトを見ている登録会員を閲覧ソフト(ブラウザー)の端に表示。会員間でチャット形式のやりとりができる」のだそうです。
「動画視聴や物品販売など同一サイトを見ている会員同士、共通の話題が見つけやすく会話が弾むという」。同じサイトを閲覧しているという「共通点」が、見知らぬ同士を引き寄せ合うわけです。
スピーキーは、専用ソフトをダウンロードして使います。ログインすると、アバター(ネット上の分身)が表示されます。チャットができるだけでなく、「利用者同士が連れ立って別のサイトに移動する機能も搭載」しているそうです。
利用は無料ですが、専用画面にバナー広告を表示して収益を上げるモデルです。「会員属性やサイト閲覧履歴などに応じて効率的な広告を表示できる」、いわゆる行動ターゲティング広告の手法が使われます。
他にも同様のサービスがあり、「昨年夏に準備版を開設したウェブリンは、早くも200万人の登録者を獲得」しているそうです。広告モデルはまだ確立しているとは言えず、「異業種と提携して活用方法を模索している」段階だそうですが。
いずれにしろ、何か「共通点」を軸にすることで、交流チャンスが生まれるという原理が働いています。ビジネスの観点で見れば、交流は口コミのチャンスでもあります。
スピーキーの場合、「会員の閲覧履歴が蓄積される」ので、「このサイトを見ている人はこんなサイトも見ています」といった推薦機能も備わります。好みが共通している相手を介し、今まで知らなかったサイトをみつけることもできるわけです。
サイト運営者にしてみれば、自サイトが閲覧される可能性が広がります。とは言え逆に、自サイトからライバルサイトに閲覧者が流れる可能性も増大します。検索エンジン経由でサイトがアクセスされるのを「縦糸」だとすれば、スピーキーのようなサービスを経由する場合は「横糸」だと言えるでしょう。
従来の「横糸」は、リンクを貼るかどうか、サイト運営者の裁量に任されていましたが、そうも行かなくなってきます。利用者にとっては便利なことですが、サイト間の比較・競争は、縦糸・横糸の両面で行なわれるようになります。
それはすなわち、優勝劣敗が、よりはっきりするようになるということです。淘汰の波が押し寄せ、「本物」だけが生き残ります。サイトの選別が、「縦糸」である検索エンジン任せでなくなれば、ネット上での競争のルールも、現在とは変わらざるを得なくなるでしょうね。
【今日の教訓】
あなたの企業では、サイト閲覧者の行動をどこまで把握しているだろうか。スピーキーやウェブリンのようなサービスが普及すれば、他の誰を連れてきてくれるかまで把握することが必要となる。淘汰の波を勝ち残る策を、今のうちから考えておこう。
<参考:日経産業新聞 2009.01.27【3面】>


 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン