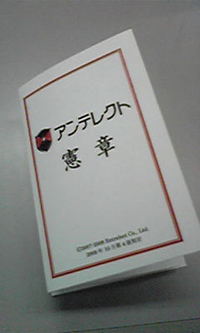【残念なお知らせ】諸般の事情により、クォーター大阪暮らしは2009年11月末をもって終了することとなりました。これまでのご愛顧に心より感謝申し上げます。今後はこちらのブログで記事を提供してまいります。よろしくお願いします。
2009年02月04日
店内在庫の削減が、なぜ調剤事業強化につながるのか?
経営にはバランスが必要だと言えば、そのとおりだと思う人は多いでしょう。しかし、戦略に関して言えば、「選択と集中」という言葉が示すように、あえてバランスを崩すことが必要となります
よく言われるのが、「強み」に集中せよということです。総花的な施策は、結局のところ、たいした成果を生むことはできません。劇的な成果は、劇的なアンバランスから生まれます。
何に集中すべきかが明確に意識されていれば、次の打ち手をどうするかは、自明の理となります。その前提は、戦略が明確になっているか、すなわち、どう戦うべきかがわかっているということでしょう。
2月4日付けの日経MJ(流通新聞)に、ドラッグストアの「セガミメディクスが調剤事業の強化に向けて、店内在庫の削減に努めている」という記事が掲載されています。
在庫を削減して、資金効率を高めるのは、どの企業も目指すところでしょう。セガミの場合、「自動発注システムに頼っていた注文方法の見直し」を行なうことで、それを実現します。
記事によれば、自動発注システムにも限界があるため、「立地環境に精通した店長」が、天候や近隣のイベントなどを勘案し、発注を決めるようにしたのだそうです。
それはよいとして、では、店内在庫の削減が、どうして調剤事業の強化につながるのでしょうか。発注の精度を高めることが、セガミの「強み」とどう結びつくのでしょうか。記事を読み進めていくと、そのロジックがわかります。
在庫を削減することで、「約500平米の店舗の場合、一割程度とされる倉庫面積を縮小させることができるようになる」そうです。その「空いた空間を調剤室の一部として活用すること」ができるようになります。
記事によれば、セガミはもともと「調剤事業に強み」があります。「現在の同事業の年間売上高は160億円で業界首位だ」そうです。それでも、現時点での調剤併設率は17%にとどまります。つまり、「強み」を伸ばす余地は、まだまだあるということなのです。
「強み」をどうやって伸ばすかを考えるには、何が制約要因になっているかを分析してみるのが有効です。セガミの場合、それは店舗スペースであり、余剰な在庫を抱えていることが問題として認識されたわけです。
発注精度を高め、欠品を防止し、適切な品揃えを実現できれば、それだけでも「強み」となり得ます。しかし、真の狙いは、その先にある、調剤事業の強化にあります。
「強み」のさらなる強化はアンバランスをもたらしますが、とは言え、人間の体のように、各業務は相互に連携していますので、特化した部分への集中は、他の部分の変革を要求します。その意味で、経営のバランスを考えることが大切なのです。
一方で調剤事業を強化し、他方で発注精度を高めておこうというのは、総花的な発想に近いでしょう。そうではなく、調剤事業のさらなる強化のために、発注精度向上にも取り組む。それが「選択と集中」であり、真の意味での経営のバランスだと言えます。
「強み」を強化することを徹底的に考えると、それは部分的な強化にとどまらず、あらゆる面に変革が要求されます。それは決して、総花的ということではありません。
【今日の教訓】
あなたの企業では、一つの明確な戦略方針に基づいた「選択と集中」がなされているだろうか。それは必ずしも社内の特定部分に特化することではない。むしろ、全社の各部分が、戦略方針に則って変革せざるを得ないという影響が及ぶと考えた方がよい。
<参考:日経MJ(流通新聞) 2009.02.04【5面】>
よく言われるのが、「強み」に集中せよということです。総花的な施策は、結局のところ、たいした成果を生むことはできません。劇的な成果は、劇的なアンバランスから生まれます。
何に集中すべきかが明確に意識されていれば、次の打ち手をどうするかは、自明の理となります。その前提は、戦略が明確になっているか、すなわち、どう戦うべきかがわかっているということでしょう。
2月4日付けの日経MJ(流通新聞)に、ドラッグストアの「セガミメディクスが調剤事業の強化に向けて、店内在庫の削減に努めている」という記事が掲載されています。
在庫を削減して、資金効率を高めるのは、どの企業も目指すところでしょう。セガミの場合、「自動発注システムに頼っていた注文方法の見直し」を行なうことで、それを実現します。
記事によれば、自動発注システムにも限界があるため、「立地環境に精通した店長」が、天候や近隣のイベントなどを勘案し、発注を決めるようにしたのだそうです。
それはよいとして、では、店内在庫の削減が、どうして調剤事業の強化につながるのでしょうか。発注の精度を高めることが、セガミの「強み」とどう結びつくのでしょうか。記事を読み進めていくと、そのロジックがわかります。
在庫を削減することで、「約500平米の店舗の場合、一割程度とされる倉庫面積を縮小させることができるようになる」そうです。その「空いた空間を調剤室の一部として活用すること」ができるようになります。
記事によれば、セガミはもともと「調剤事業に強み」があります。「現在の同事業の年間売上高は160億円で業界首位だ」そうです。それでも、現時点での調剤併設率は17%にとどまります。つまり、「強み」を伸ばす余地は、まだまだあるということなのです。
「強み」をどうやって伸ばすかを考えるには、何が制約要因になっているかを分析してみるのが有効です。セガミの場合、それは店舗スペースであり、余剰な在庫を抱えていることが問題として認識されたわけです。
発注精度を高め、欠品を防止し、適切な品揃えを実現できれば、それだけでも「強み」となり得ます。しかし、真の狙いは、その先にある、調剤事業の強化にあります。
「強み」のさらなる強化はアンバランスをもたらしますが、とは言え、人間の体のように、各業務は相互に連携していますので、特化した部分への集中は、他の部分の変革を要求します。その意味で、経営のバランスを考えることが大切なのです。
一方で調剤事業を強化し、他方で発注精度を高めておこうというのは、総花的な発想に近いでしょう。そうではなく、調剤事業のさらなる強化のために、発注精度向上にも取り組む。それが「選択と集中」であり、真の意味での経営のバランスだと言えます。
「強み」を強化することを徹底的に考えると、それは部分的な強化にとどまらず、あらゆる面に変革が要求されます。それは決して、総花的ということではありません。
【今日の教訓】
あなたの企業では、一つの明確な戦略方針に基づいた「選択と集中」がなされているだろうか。それは必ずしも社内の特定部分に特化することではない。むしろ、全社の各部分が、戦略方針に則って変革せざるを得ないという影響が及ぶと考えた方がよい。
<参考:日経MJ(流通新聞) 2009.02.04【5面】>
Posted by HANK@森 at 20:43│Comments(0)
│ビジネス
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。


 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン