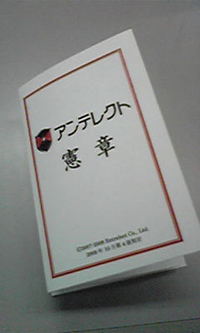【残念なお知らせ】諸般の事情により、クォーター大阪暮らしは2009年11月末をもって終了することとなりました。これまでのご愛顧に心より感謝申し上げます。今後はこちらのブログで記事を提供してまいります。よろしくお願いします。
2009年08月05日
「フレスコ」っていうスーパー、知ってますか?
中小企業の強みは、小回りがきくこと、すなわち機動力だと言われます。
組織が小さい分、意思決定が迅速にできますし、仕組みやルールがキチンと出来ていないことで、融通を利かせられる面もあります。時には、採算の合わないことでも平気でやります。
企業組織が大きくなってくると、なかなかそうも行かなくなりますね。
トップの「鶴の一声」でもあれば別でしょうが、採算割れは厳しく責任を問われますし、効率も追求されます。
以前、某中小製造メーカーのコンサルティングをさせていただいたことがありますが、大企業からヘッドハンティングされてきた工場長と社長との間の確執があったことを思い出します。
生産ラインで手が空いた従業員はどうすべきでしょうか。自主的に他のラインを手伝うべきだというのが社長の考えです。
ですが工場長は、それをさせず、黙って座ってろと指示しました。
工場長に言わせれば、勝手に他のラインを手伝うことをされると、生産ラインの負荷の偏りが見えにくくなってしまいますし、ライン毎の正確な損益も、わからなくなってしまいます。ですので、黙って座ってろ、という話になるのです。
どちらが正しいのか、という話をするつもりはありません。
どこに視点を置くかにより、判断が変わってくるということです。中小企業と大企業とでは、明らかに視点が違ってきます。
8月5日付けの日経MJ(流通新聞)に、「近畿地区で展開する食品スーパー『フレスコ』が堅調だ」という記事が掲載されています。その要因は、「買い物客から要望があった商品を積極的に取り入れる柔軟な品ぞろえ」にあるのだそうです。
フレスコのこのやり方について、記事は「本部主導の商品政策(MD)やチェーン運営と一線を画し、大手・中堅スーパーとの違いを打ち出している」と解説しています。
片岡孝一社長は、「若く完成していない会社だからこそ、チェーンストアの常識にとらわれない柔軟な店づくりをしていく」とコメントしています。冒頭で述べた、中小企業の機動力を発揮しているような格好になります。
作業効率は、決してよくありません。
記事によれば、「狭い店舗でお客さんの求める商品を並べるため、必要な数を陳列できない商品は1日に何度も品出しせざるを得」ないといったことが起きています。要望された商品が入荷したら、メールや電話で知らせるといったことまでしています。
効率は悪いように見えますが、「2009年2月期の売上高は前の期比7%増の376億円」と成果を上げています。「利用者の声を無駄にしない」ことで、「信用の地道な積み重ねを重視」した結果です。「効率」よりも「信用」。ここに他との視点の違いが見えてきます。
興味深いのは、「出店後に品ぞろえを地域ニーズに合わせて固定客をつかんでいく手法のため、チラシによる販促費をあまりかけない」ということです。
それは数字にも現われていて、「フレスコの店舗は初年度の売り上げは小さくても、2年目以降に2ケタ増など高い伸びを示すことが多い」とのことです。
言ってみれば、顧客により店がつくられていく形になります。顧客の声を聞き、ニーズに対応していくのは、どの企業もしていることのはずですが、現実には、「効率」を言い訳に、フレスコほどは徹底できないことが多いのでしょう。
チェーンストアの常識からすれば、ちょっとしたカルチャーショックだと言えると思います。ですが、特に不景気にあっては、固定客をしっかりと確保することが定石です。
何度も品出しをすることも不効率ですが、固定客を確保できず、安売りチラシを大量にばらまき、“浮気症”の顧客を集客すること、もっと不効率でしょう。
「効率」に対する視点についても、変えて考えてみることが必要ですね。
【今日の教訓】
あなたの企業では、どのような観点で「効率」を追求しているだろうか。効率が良いと思われるやり方は、本当にそうなのだろうか? 逆は、どうだろうか? 時には視点を変え、そのことについて考えてみよう。もしかしたら、業界の常識を覆すようなやり方も、あり得るのかも知れない。
<参考:日経MJ(流通新聞) 2009.08.05【5面】>
組織が小さい分、意思決定が迅速にできますし、仕組みやルールがキチンと出来ていないことで、融通を利かせられる面もあります。時には、採算の合わないことでも平気でやります。
企業組織が大きくなってくると、なかなかそうも行かなくなりますね。
トップの「鶴の一声」でもあれば別でしょうが、採算割れは厳しく責任を問われますし、効率も追求されます。
以前、某中小製造メーカーのコンサルティングをさせていただいたことがありますが、大企業からヘッドハンティングされてきた工場長と社長との間の確執があったことを思い出します。
生産ラインで手が空いた従業員はどうすべきでしょうか。自主的に他のラインを手伝うべきだというのが社長の考えです。
ですが工場長は、それをさせず、黙って座ってろと指示しました。
工場長に言わせれば、勝手に他のラインを手伝うことをされると、生産ラインの負荷の偏りが見えにくくなってしまいますし、ライン毎の正確な損益も、わからなくなってしまいます。ですので、黙って座ってろ、という話になるのです。
どちらが正しいのか、という話をするつもりはありません。
どこに視点を置くかにより、判断が変わってくるということです。中小企業と大企業とでは、明らかに視点が違ってきます。
8月5日付けの日経MJ(流通新聞)に、「近畿地区で展開する食品スーパー『フレスコ』が堅調だ」という記事が掲載されています。その要因は、「買い物客から要望があった商品を積極的に取り入れる柔軟な品ぞろえ」にあるのだそうです。
フレスコのこのやり方について、記事は「本部主導の商品政策(MD)やチェーン運営と一線を画し、大手・中堅スーパーとの違いを打ち出している」と解説しています。
片岡孝一社長は、「若く完成していない会社だからこそ、チェーンストアの常識にとらわれない柔軟な店づくりをしていく」とコメントしています。冒頭で述べた、中小企業の機動力を発揮しているような格好になります。
作業効率は、決してよくありません。
記事によれば、「狭い店舗でお客さんの求める商品を並べるため、必要な数を陳列できない商品は1日に何度も品出しせざるを得」ないといったことが起きています。要望された商品が入荷したら、メールや電話で知らせるといったことまでしています。
効率は悪いように見えますが、「2009年2月期の売上高は前の期比7%増の376億円」と成果を上げています。「利用者の声を無駄にしない」ことで、「信用の地道な積み重ねを重視」した結果です。「効率」よりも「信用」。ここに他との視点の違いが見えてきます。
興味深いのは、「出店後に品ぞろえを地域ニーズに合わせて固定客をつかんでいく手法のため、チラシによる販促費をあまりかけない」ということです。
それは数字にも現われていて、「フレスコの店舗は初年度の売り上げは小さくても、2年目以降に2ケタ増など高い伸びを示すことが多い」とのことです。
言ってみれば、顧客により店がつくられていく形になります。顧客の声を聞き、ニーズに対応していくのは、どの企業もしていることのはずですが、現実には、「効率」を言い訳に、フレスコほどは徹底できないことが多いのでしょう。
チェーンストアの常識からすれば、ちょっとしたカルチャーショックだと言えると思います。ですが、特に不景気にあっては、固定客をしっかりと確保することが定石です。
何度も品出しをすることも不効率ですが、固定客を確保できず、安売りチラシを大量にばらまき、“浮気症”の顧客を集客すること、もっと不効率でしょう。
「効率」に対する視点についても、変えて考えてみることが必要ですね。
【今日の教訓】
あなたの企業では、どのような観点で「効率」を追求しているだろうか。効率が良いと思われるやり方は、本当にそうなのだろうか? 逆は、どうだろうか? 時には視点を変え、そのことについて考えてみよう。もしかしたら、業界の常識を覆すようなやり方も、あり得るのかも知れない。
<参考:日経MJ(流通新聞) 2009.08.05【5面】>
Posted by HANK@森 at 18:07│Comments(0)
│ビジネス
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。


 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン