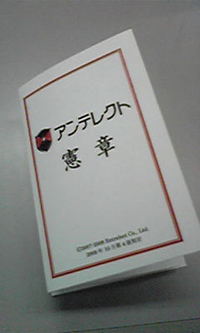【残念なお知らせ】諸般の事情により、クォーター大阪暮らしは2009年11月末をもって終了することとなりました。これまでのご愛顧に心より感謝申し上げます。今後はこちらのブログで記事を提供してまいります。よろしくお願いします。
2009年06月09日
絵画の価格をサイズで決める
週末起業フォーラム会員に対するメールでのコンサルティングを行なっています。よくある質問として、「この商品・サービスは、価格をいくらにしたらよいでしょうか」というものがあります。
基本的には、同業他社を調べて相場を把握することと、かかる原価・経費を積み上げてみることの両面で考えるようにアドバイスします。商品・サービスの種類が多岐にわたる、あるいはカスタムメイドの場合は、積算基準も設定する必要があります。
いずれにしろ、価格設定というのは、悩ましい問題です。積算基準を設定して見積もってみると、一部の商品については妥当な価格水準となるが、他の商品については不適切、といったことがあり得ます。
積算の基準は、いわゆる「○○あたり」のような設定になるのが一般的でしょう。コンサルティングやコーチングなら、「1時間あたり」あるいは「1ヶ月あたり」といった具合です。
コンサルティング/コーチングのようなサービスの場合、誰もが認める積算基準が存在するわけではありません。ベテランと駆け出しとで、価格が全く同じというのもおかしいでしょう。
物販でも、絵画のような美術品では、価格設定は明快ではありません。コンサルタントやコーチのように、アーチストの技量は千差万別ですし、作品ごとの評価もまちまちとなりがちです。ですが、基準を設定しようと思えば、できないことはないようです。
6月9日付けの日経産業新聞に、カヤックという会社が運営する「アートメーター」というサイトについての記事が掲載されています。このサイトは、「絵画の寸法で販売価格が決まる方式に特徴がある」のだそうです。
この記事の趣旨は、アートメーターが「海外展開に乗り出す」ということです。「日本文化に興味を持つ外国人からの購入希望があり、需要が高まると判断した」という背景があります。
ですが、今回は、「絵画の寸法で販売価格が決まる」という点に着目したいと思います。上述のように、価格を決定する基準は悩ましいと思うからです。
実を言えば、寸法で絵画の価格を決めるというのは、アートメーターの専売特許というわけではありません。「号あたりいくら」という目安は、以前から知られています。(もちろん、画家のレベルにより、「号あたり」の価格水準は変動します)
実際のところ、どうなのでしょうか。サイズが大きければ、絵の具やキャンバスの価格(原価)は高くなります。ですが、高額な絵画の価格からすれば、誤差の範囲程度の話です。
絵を描く手間については、やはり大きい方がかかりそうです。とは言え、2倍のサイズの絵を描くのに、2倍の時間がかかるというわけではないようです。逆に、極端に小さいサイズの絵を描く方が、よほど手間がかかります。
このように、サイズで価格を決めるのは、現実のところ、原価からみた妥当性は、必ずしも高くありません。ですが視点を変え、買い手の立場からみると、非常にわかりやすい価格積算方式だということになります。
アートメーターのサイトをみると、「絵の測り売り」と謳っていて、記事で述べられているように、それを特徴として打ち出しています。価格が「わかりやすい」ことは、アドバンテージなのです。
一皿100円の回転寿司は、価格のわかりやすさが支持され、日本人(そして世界中で)の外食に大きな影響を与えました。「時価」のような不透明性を排除したアイデアの勝利だと言えるでしょう。
絵画もまた、かつての寿司と同じように、素人には、いくらなのか見当がつかない商品であったりします。価格決定の透明性を高める余地があるわけです。
商品・サービス価格の決定は悩ましく、価格設定基準も明確にしたいという気持ちは、売り手側が抱える問題です。ですが一方、実は買い手にも、それは求められているのです。
特に「わかりやすい」ことが必要ですね。その観点で、価格水準のみならず、価格設定方法の透明性についても、考え直してみてはどうでしょうか。
【今日の教訓】
あなたの企業が提供する商品・サービスの価格設定基準は、顧客からみてわかりやすいものだろうか。「○○あたりいくら」のように、思いっきりわかりやすくするだけでも、自社の特徴を強力に打ち出していくことができる。見直してみよう。
<参考:日経産業新聞 2009.06.09【4面】>
基本的には、同業他社を調べて相場を把握することと、かかる原価・経費を積み上げてみることの両面で考えるようにアドバイスします。商品・サービスの種類が多岐にわたる、あるいはカスタムメイドの場合は、積算基準も設定する必要があります。
いずれにしろ、価格設定というのは、悩ましい問題です。積算基準を設定して見積もってみると、一部の商品については妥当な価格水準となるが、他の商品については不適切、といったことがあり得ます。
積算の基準は、いわゆる「○○あたり」のような設定になるのが一般的でしょう。コンサルティングやコーチングなら、「1時間あたり」あるいは「1ヶ月あたり」といった具合です。
コンサルティング/コーチングのようなサービスの場合、誰もが認める積算基準が存在するわけではありません。ベテランと駆け出しとで、価格が全く同じというのもおかしいでしょう。
物販でも、絵画のような美術品では、価格設定は明快ではありません。コンサルタントやコーチのように、アーチストの技量は千差万別ですし、作品ごとの評価もまちまちとなりがちです。ですが、基準を設定しようと思えば、できないことはないようです。
6月9日付けの日経産業新聞に、カヤックという会社が運営する「アートメーター」というサイトについての記事が掲載されています。このサイトは、「絵画の寸法で販売価格が決まる方式に特徴がある」のだそうです。
この記事の趣旨は、アートメーターが「海外展開に乗り出す」ということです。「日本文化に興味を持つ外国人からの購入希望があり、需要が高まると判断した」という背景があります。
ですが、今回は、「絵画の寸法で販売価格が決まる」という点に着目したいと思います。上述のように、価格を決定する基準は悩ましいと思うからです。
実を言えば、寸法で絵画の価格を決めるというのは、アートメーターの専売特許というわけではありません。「号あたりいくら」という目安は、以前から知られています。(もちろん、画家のレベルにより、「号あたり」の価格水準は変動します)
実際のところ、どうなのでしょうか。サイズが大きければ、絵の具やキャンバスの価格(原価)は高くなります。ですが、高額な絵画の価格からすれば、誤差の範囲程度の話です。
絵を描く手間については、やはり大きい方がかかりそうです。とは言え、2倍のサイズの絵を描くのに、2倍の時間がかかるというわけではないようです。逆に、極端に小さいサイズの絵を描く方が、よほど手間がかかります。
このように、サイズで価格を決めるのは、現実のところ、原価からみた妥当性は、必ずしも高くありません。ですが視点を変え、買い手の立場からみると、非常にわかりやすい価格積算方式だということになります。
アートメーターのサイトをみると、「絵の測り売り」と謳っていて、記事で述べられているように、それを特徴として打ち出しています。価格が「わかりやすい」ことは、アドバンテージなのです。
一皿100円の回転寿司は、価格のわかりやすさが支持され、日本人(そして世界中で)の外食に大きな影響を与えました。「時価」のような不透明性を排除したアイデアの勝利だと言えるでしょう。
絵画もまた、かつての寿司と同じように、素人には、いくらなのか見当がつかない商品であったりします。価格決定の透明性を高める余地があるわけです。
商品・サービス価格の決定は悩ましく、価格設定基準も明確にしたいという気持ちは、売り手側が抱える問題です。ですが一方、実は買い手にも、それは求められているのです。
特に「わかりやすい」ことが必要ですね。その観点で、価格水準のみならず、価格設定方法の透明性についても、考え直してみてはどうでしょうか。
【今日の教訓】
あなたの企業が提供する商品・サービスの価格設定基準は、顧客からみてわかりやすいものだろうか。「○○あたりいくら」のように、思いっきりわかりやすくするだけでも、自社の特徴を強力に打ち出していくことができる。見直してみよう。
<参考:日経産業新聞 2009.06.09【4面】>
Posted by HANK@森 at 17:11│Comments(0)
│ビジネス
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。


 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン