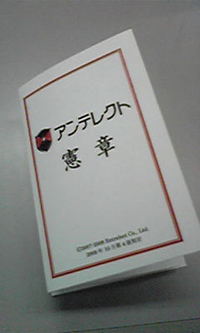【残念なお知らせ】諸般の事情により、クォーター大阪暮らしは2009年11月末をもって終了することとなりました。これまでのご愛顧に心より感謝申し上げます。今後はこちらのブログで記事を提供してまいります。よろしくお願いします。
2008年11月19日
下請けからの転換を推進-パートナーとの関係を見直す
週末起業フォーラムを通じて起業支援活動に取り組み、自分でも起
業して強く感じるのは、「一人では何もできない」ということです
ね。お客さんも含め、協力者の力を借りることが、どうしても必要
となります。
ビジネスに取り組む以上、経営資源を確保しなくてはなりませんが、
起業当初は、ほとんど何もない状態です。となると、他者の持つ経
営資源をどれだけ上手に使わせてもらうかが、極めて重要な課題な
んですね。
社内の資源を使う場合、それを上手に配分する技量が必要です。外
部の資源についても同様で、たとえばパートナーをどのように選び、
何を委託するのか等をよく考えて動かないと、なかなか成功できま
せん。
11月19日付けの日本経済新聞(埼玉版)に、埼玉県羽生市にある
小島染織工業という会社についての記事が掲載されています。同社
が「下請けから製造小売りへの転換を進めている」と報じています。
記事によれば、同社は「130年以上の歴史を持つ老舗の染織加工メ
ーカー」です。元々は、「農業の副業として当時の作業着として使
う農作業用のまた引きや足袋を生産し始めたのが始まり」だそうで
す。
現在は「剣道着やのれん生地の染織加工」がメインのようですが、
記事には「下請け」とあるので、自社ブランドで販売しているので
はないのでしょう。小島秀之社長によれば、「今後の需要拡大は見
込めない」とのことです。
下請けの場合、発注企業も「協力者」の一つであり、ビジネスパー
トナーとしては、ありがたい存在でもあります。しかし時流を考え
れば、見直すことが必要だというわけですね。
記事によれば、「藍染め関連の事業者数はここ10年は横ばいで推
移しているが、約85年前と比べると2%程度にまで激減している」
とのことです。なかなか、厳しいですね。
小島社長は元々、伊藤忠商事に勤務していたのですが、先代の死去
に伴い社長に就任しました。「需要拡大の見込めない商品ばかり作っ
ていて売上は減る一方だった」ことに、危機感を募らせました。
そこで取り組み始めたのが「新商品の開発」であり、今回の記事に
ある「製造小売り」へとつながります。とは言え、「最初に企画し
た藍染めの手ぬぐいとバンダナは全く売れず大失敗だった」そうで
す。
しかしその後、ノウハウを蓄積し、「2008年に売り出したエコバッ
グやTシャツは比較的好調で」、「次なる商品として期待がかかる
のはジーンズだ」といいます。
同じ藍染めでも、商品企画を工夫すれば、展望は見いだせるもので
す。色落ちのジーンズあたりは、「こだわりのある消費者の購買意欲
を刺激する」魅力的な商品だと思います。
そう考えると、小島染織工業をはじめとする染織業者を下請けとし
て使っていた発注者は、何をやっていたのかでしょうか、という気
がします。
推測ですが、藍染め製品だけを扱っていたわけではないのかも知れ
ません。他に売れるものがあれば、藍染めの新商品を企画しなけれ
ばならない義理もないでしょう。
でも染織業者からすれば、パートナーとしては、実に頼りない存在
だということになりますね。
小島染織工業については、「企画力を磨くため他者との共同開発に
も取り組み始め、製造小売りのノウハウを蓄積」する努力をしてき
たそうです。活路を見出すために、新たなパートナーを開拓したわ
けですね。
新たな戦略の構築は、経営資源の再配分を伴います。そして、持て
る資源上の戦略を展開することはできません。
外部の協力者という資源についても同様で、パートナーとの関係の
見直しに後れをとると、新たな展望を拓けないことになってしまう
のです。
<参考:日本経済新聞 2008.11.19【埼玉23面】>
業して強く感じるのは、「一人では何もできない」ということです
ね。お客さんも含め、協力者の力を借りることが、どうしても必要
となります。
ビジネスに取り組む以上、経営資源を確保しなくてはなりませんが、
起業当初は、ほとんど何もない状態です。となると、他者の持つ経
営資源をどれだけ上手に使わせてもらうかが、極めて重要な課題な
んですね。
社内の資源を使う場合、それを上手に配分する技量が必要です。外
部の資源についても同様で、たとえばパートナーをどのように選び、
何を委託するのか等をよく考えて動かないと、なかなか成功できま
せん。
11月19日付けの日本経済新聞(埼玉版)に、埼玉県羽生市にある
小島染織工業という会社についての記事が掲載されています。同社
が「下請けから製造小売りへの転換を進めている」と報じています。
記事によれば、同社は「130年以上の歴史を持つ老舗の染織加工メ
ーカー」です。元々は、「農業の副業として当時の作業着として使
う農作業用のまた引きや足袋を生産し始めたのが始まり」だそうで
す。
現在は「剣道着やのれん生地の染織加工」がメインのようですが、
記事には「下請け」とあるので、自社ブランドで販売しているので
はないのでしょう。小島秀之社長によれば、「今後の需要拡大は見
込めない」とのことです。
下請けの場合、発注企業も「協力者」の一つであり、ビジネスパー
トナーとしては、ありがたい存在でもあります。しかし時流を考え
れば、見直すことが必要だというわけですね。
記事によれば、「藍染め関連の事業者数はここ10年は横ばいで推
移しているが、約85年前と比べると2%程度にまで激減している」
とのことです。なかなか、厳しいですね。
小島社長は元々、伊藤忠商事に勤務していたのですが、先代の死去
に伴い社長に就任しました。「需要拡大の見込めない商品ばかり作っ
ていて売上は減る一方だった」ことに、危機感を募らせました。
そこで取り組み始めたのが「新商品の開発」であり、今回の記事に
ある「製造小売り」へとつながります。とは言え、「最初に企画し
た藍染めの手ぬぐいとバンダナは全く売れず大失敗だった」そうで
す。
しかしその後、ノウハウを蓄積し、「2008年に売り出したエコバッ
グやTシャツは比較的好調で」、「次なる商品として期待がかかる
のはジーンズだ」といいます。
同じ藍染めでも、商品企画を工夫すれば、展望は見いだせるもので
す。色落ちのジーンズあたりは、「こだわりのある消費者の購買意欲
を刺激する」魅力的な商品だと思います。
そう考えると、小島染織工業をはじめとする染織業者を下請けとし
て使っていた発注者は、何をやっていたのかでしょうか、という気
がします。
推測ですが、藍染め製品だけを扱っていたわけではないのかも知れ
ません。他に売れるものがあれば、藍染めの新商品を企画しなけれ
ばならない義理もないでしょう。
でも染織業者からすれば、パートナーとしては、実に頼りない存在
だということになりますね。
小島染織工業については、「企画力を磨くため他者との共同開発に
も取り組み始め、製造小売りのノウハウを蓄積」する努力をしてき
たそうです。活路を見出すために、新たなパートナーを開拓したわ
けですね。
新たな戦略の構築は、経営資源の再配分を伴います。そして、持て
る資源上の戦略を展開することはできません。
外部の協力者という資源についても同様で、パートナーとの関係の
見直しに後れをとると、新たな展望を拓けないことになってしまう
のです。
<参考:日本経済新聞 2008.11.19【埼玉23面】>
Posted by HANK@森 at 19:48│Comments(0)
│ビジネス
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。


 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン